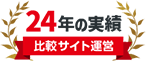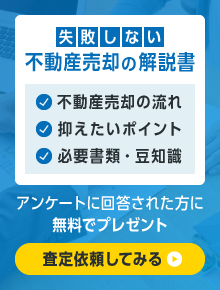不動産売却にかかる税金と税率をわかりやすく解説

個人が不動産売却をする際にかかる税金には、売却益(譲渡所得)に対してかかる税金と、売却手続きにかかる税金があります。それぞれの種類は以下の通りです。
売却益(譲渡所得)に対してかかる税金
- 所得税
- 住民税
- 復興特別所得税
売却手続きにかかる税金
- 印紙税
- 登録免許税
以下の記事では、これらの税金の詳細と、特例などを詳しく解説しています。
- 不動産売却にかかる税金の種類
- 譲渡所得にかかる税金の計算方法
- 不動産売却手続きにかかる税金の金額・税率

【監修】藤沼寛夫 公認会計士・税理士 アカウントエージェント株式会社 代表取締役 藤沼会計事務所 代表社員 2014年 EY新日本有限責任監査法人 入社 2018年 中堅会計事務所 入所 2019年 藤沼会計事務所 開業 2020年 アカウントエージェント株式会社 設立 会計税務に関する幅広いサービスを提供している。 アカウントエージェント株式会社ホームページ https://a-agent.co.jp/
不動産売却益(譲渡所得)にかかる税金とその税率
.webp?q=50)
不動産売却益は「一時所得」と思われがちですが、正しい税制上の分類は「譲渡所得」です。譲渡所得とは、不動産等の資産を売却した際に得た利益(収入)のことを指します。
譲渡所得には、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。これらの税額を求めるためには、まず譲渡所得金額の算出が必要です。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得金額は、下記の式から計算します。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
※
取得費:購入にかけた費用のこと
譲渡費用:売却にかけた費用のこと
売却金額から、取得費と譲渡費用を引いた金額が譲渡所得です。
なお、売却によって損失が出た場合、譲渡所得ではなく譲渡損失になります。詳しくは後述します。
取得費・譲渡費用に含まれるもの
取得費は、購入にあたって必要とした費用、譲渡費用は売却するために必要になった費用です。取得費・譲渡費用それぞれに含まれるもの以下の通りです。
- 仲介手数料
- 不動産の購入金額(減価償却費相当額を差し引いた金額)
- 購入時に納めた登録免許税、不動産取得税、印紙税
- 造成費、解体費用
- 売るために支払った仲介手数料
- 売手が負担した印紙税
- 売主が負担した測量費
- 売るために建物を壊したときの取り壊し費用と建物の損失額
- 立退料
取得費は減価償却が必要
土地だけを売却した場合の減価償却は必要ありませんが、建物を売却した場合は減価償却を考慮する必要があります。建物は時間がたつと価値が下がるため、取得費から所有期間中の減価償却費を差し引かなければなりません。
減価償却費は、以下の計算式で求められます。
減価償却費 = 建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
償却率は、建物の構造によって異なり、居住用と事業用によっても違うので注意が必要です。居住用建物の償却率を以下に紹介します。
- 木造:0.031
- 軽量鉄骨造(骨格材3mm超4mm以下):0.025
- 鉄筋コンクリート造:0.015
譲渡所得に係る所得税・住民税・復興特別所得税の税率
譲渡所得に係る所得税・住民税・復興特別所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わります。売却した年の1月1日現在における所有期間が、5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得に分類されます。
復興特別所得税は2013年から2037年まで加算される税金です。基準所得税額の2.1%が税率となっています。
| 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | ||
|---|---|---|---|
| 所有期間 | 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例 (居住用財産を売って、一定の要件に当てはまるとき) |
| 税率 | 合計税率39.63% (所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%) | 合計税率20.315% (所得税15%・ 復興特別所得税0.315%・住民税5%) | ①課税譲渡所得6,000万円以下の部分
14.21%
(所得税10%・復興特別所得税0.21%・住民税4%)
②課税譲渡所得6,000万円超の部分 20.315% (所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%) |
特別控除・特例
不動産は必要に迫られて売却するケースも多いため、税制面の特別控除や特例などの優遇措置が設けられています。条件を満たしている場合は利用すると良いでしょう。以下は、代表的な特別控除・特例の例です。
| 状況 | 控除の詳細 |
|---|---|
| マイホームの売却 | 譲渡所得から最大3,000万円控除される |
| 所有10年超のマイホームの売却 | 所得税・復興特別所得税・住民税が最大14.21%まで軽減される |
| マイホームの買い替え | 発生した譲渡所得を将来に繰り延べられる |
| 相続した不動産の売却 | 譲渡所得から最大3,000万円控除される |
特例はこのほかにもあるため、当てはまるものがないか一度確認してみてください。
譲渡所得金額に応じた税額の早見表
所有期間・特例を踏まえた、譲渡所得金額別の早見表は以下の通りです。マイホームの場合と、相続した家の場合とで税額が変わります。
| 譲渡所得金額 | 5年以下の所有 | 5年超10年以下の所有 | 10年超の所有 |
|---|---|---|---|
| ~3,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 396万円 | 203万円 | 142万円 |
| 5,000万円 | 792万円 | 406万円 | 284万円 |
| 6,000万円 | 1,188万円 | 609万円 | 426万円 |
| 7,000万円 | 1,585万円 | 812万円 | 568万円 |
| 8,000万円 | 1,981万円 | 1,015万円 | 710万円 |
| 9,000万円 | 2,377万円 | 1,218万円 | 852万円 |
| 1億円 | 2,774万円 | 1,422万円 | 994万円 |
※「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を適用して計算
| 譲渡所得金額 | 5年以下の所有 | 5年超の所有 |
|---|---|---|
| ~3,000万円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 396万円 | 203万円 |
| 5,000万円 | 792万円 | 406万円 |
| 6,000万円 | 1,188万円 | 609万円 |
| 7,000万円 | 1,585万円 | 812万円 |
| 8,000万円 | 1,981万円 | 1,015万円 |
| 9,000万円 | 2,377万円 | 1,218万円 |
| 1億円 | 2,774万円 | 1,422万円 |
※「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用して計算
不動産売却の手続きにかかる税金
不動産売却の手続きで納めなければならない税金は、印紙税と登録免許税の2つです。それぞれの概要を紹介します。
印紙税
印紙税とは、印紙税法で定められた契約書や領収書など、特定の文書に対して課税される税金のことです。不動産譲渡に関する契約書は、印紙税法に指定される文書に該当し、印紙を購入して契約書に貼り付ける必要があります。
印紙税の納税額は契約金額によって、下表のように異なります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5000円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
ただし、令和6年3月31日までに作成される契約書に関しては、軽減措置が適用されます。
登録免許税
不動産を売却して名義を変えるには、法務局の登記簿に「所有権移転登記」をしなければなりません。この登記手続きのために、登録免許税がかかります。登記申請時に印紙を貼って納税しますが、司法書士報酬などの実費とともに請求されるのが一般的です。
登録免許税は、登記の種類によって税率が異なります。不動産売却によって所有権を移転する場合の税額は「固定資産税評価額 × 2%」です。しかし、登録免許税にも軽減措置があり、令和8年3月31日までは「固定資産税評価額 × 1.5%」が適用されます。
不動産売却にかかる税金に関するよくある疑問
不動産売却の税金に関して、損失が出た場合の確定申告や、納税のタイミングなど、よくある疑問の答えを解説していきます。
売却で損失が出た場合確定申告は不要?
不動産売却で非課税になるのは、通算で損失になった場合で、この場合は確定申告をしなくても問題はありません。しかし、損失が出ても確定申告をすれば、不動産売却額と年収を合算し相殺する損益通算や、損失額を翌年に持ち越せる繰越控除などの特例を受けられます。
そのため、損失が出ても確定申告をしておく方がよいでしょう。以下はマイホームの売却で損失が出た場合に適用できる特例です。
- 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
税金を支払うタイミングは?
不動産売却にかかる各種税金の支払いタイミングは以下の通りです。
| 税金の種類 | 支払うタイミング |
|---|---|
| 所得税(復興特別所得税) | 現金:3月15日 口座振替:4月下旬に指定口座から引き落とし |
| 住民税 | 6月末日・8月末日・10月・翌年1月末日 (条例で定められている日) |
| 印紙税 | 不動産売買契約の締結時 |
| 登録免許税 | 所有権移転登記の日、もしくはそれ以前 |
延納できるものもありますが、利子税が上乗せされることもあるので、極力期日内に支払うようにしましょう。
税金額を簡単にシミュレーションする方法はある?
不動産売却で支払うべき税金をその都度計算するのは大変です。
税額がおおよそどの程度になるのか、簡単に知りたいなら、ズバット不動産売却のシミュレーターを利用するのがおすすめです。想定売却価格や住宅ローン残債、諸費用を入力すれば、売却後の手取り金額が算出され、税金額も詳細に表示されます。
.webp?q=50)
.webp?q=50)
.webp?q=50)
不動産を売却したら手元にいくらほど残るのか気になる方は、ぜひ以下のページからシミュレーションしてみてください。
手取り金額をシミュレーション
シミュレーション開始不動産売却にかかる税金と税率まとめ
不動産売却時は、譲渡所得・手続きそれぞれに税金が発生します。課税金額の算出方法や税率、控除などは覚えておいて損はないでしょう。
売却して損失が出た場合は課税対象にはなりませんが、控除や特例の適用を考慮して、確定申告の準備も念頭に置いておく必要があります。
不動産売却のことでお悩みでしたら、ぜひ不動産売却のズバットへご相談ください。
最大6社にまとめて査定依頼
査定依頼してみる完全無料