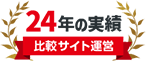不動産売買契約書とは?記載内容を総まとめ

土地やマンションなどの不動産を売買する際には、売り手と買い手との間で不動産売買契約書が交わされます。
契約書には重要な内容が記載されているため、契約を締結する前にきちんと確認することが大切です。
この記事では不動産売買契約書とは何か、記載されている内容は何かなどをわかりやすく解説します。
契約書の記載内容は注意点も併せて解説するので、不動産の売買を検討している人はぜひ役立ててください。

【監修】穂坂 潤平 宅地建物取引士。仲介営業13年(宅建は新卒の時に取得)、不動産仲介会社起業3年の経験を経てウェブクルーに入社。趣味は何でも遊びにすること。仕事では「喜ばれる仕事をして、自らも喜ぶこと」をモットーに日々ご提案しております!
不動産売買契約書とは

契約書はさまざまな取引きにおいて、記載された内容を明確にし、後日証明するために作成されます。
不動産売買契約書は、不動産の取引きに特化した契約書です。
不動産取引きでは、売り手と買い手を仲介する不動産会社が作成するのが一般的です。
契約内容が記載された書類
不動産売買契約書とは不動産の取引きにおいて、売り手と買い手が取り決めた内容が記載された書類です。
不動産取引きの場合、売り手は買い手に対して売却代金の債権があるのに対し、不動産を譲り渡す債務が生じます。
一方で買い手は売り手に対して不動産を譲り受ける債権を持つのに対し、売却代金の債務を負います。
つまり、不動産の取引きでは売り手と買い手の双方に債務者と債権者の関係が成立するというわけです。
売り手と買い手はそれぞれの債権と債務を履行できるよう、契約書に取り決めた内容を記載します。
また、売買契約の締結後、契約内容を証明する役割もあります。
契約書に記載される内容は、売却代金や支払い時期などさまざまです。
双方のトラブルを未然に防げる
民法第五百五十五条では売り手が財産権を移転する意志を示し、買い手が代金を支払う意思を示せば、双方が合意したものとして契約が成立するとされています。
つまり、口頭でも双方が合意すれば、契約が成立するということです。
しかし、口頭では契約内容を証明できないため、トラブルにつながる可能性があります。
実際のところ、不動産取引きを巡るトラブルは決して少なくありません。
国土交通省の「不動産トラブル事例データベース」では、過去に起きたさまざまなトラブルが掲載されています。
事例の中には、債権や債務の不履行といった契約内容に関するトラブルも含まれています。
売買契約の締結後にトラブルが起こる可能性があるため、契約内容を明確にし、証明できるものが必要です。
以上のような理由から、不動産を取引きする際には契約書を作成するのが一般的です。
売り手と買い手の双方が安心して取引を進めるためにも、契約書の存在は重要になります。
基本的に不動産会社が作成する
一般的な不動産取引きでは、売り手や買い手が不動産会社と媒介契約を締結し、仲介を依頼するケースがほとんどです。
媒介契約とは、不動産会社に不動産の売却活動を任せるための契約です。
売却活動には不動産売買契約書作成業務も含まれているため、売り手や買い手が作成する必要はありません。
売り手と買い手の不動産会社が異なる場合は、どちらかの業者が作成し、もう一方の業者に確認してもらう形になります。
不動産売買契約書に記載されている内容

不動産売買契約書には、売り手と買い手の間で取り決めた内容が詳細に記載されています。
記載されているおもな内容は、次の通りです。
| 不動産売買契約書に記載されている内容 | 詳細 |
|---|---|
| 取引物件の表示 | 不動産取引の対象となる物件情報を記載 |
| 売却代金・手付金の金額および支払い期日 | 売却代金および手付金の金額、それぞれの支払い期日を記載 |
| 土地の実測および代金の清算 | 実測の結果、土地の面積に誤差がある場合は、差分を土地代金として清算することを記載 |
| 所有権移転および引渡し時期 | トラブルを防ぐために、所有権移転や物件の引渡し時期を明記 |
| 付帯設備の引継 | 建物内外の設備を売り手から買い手にどこまで引渡すかを記載 |
| 負担の消除 | 物件の引渡しまでに賃借権や抵当権を消除する旨の内容を記載 |
| 各種税金の清算 | 売り手と買い手で税金をどの程度負担するかを記載 |
| 手付解除の期限 | 手付解除の有効期限を記載 |
| 契約違反による解除 | 違反した側が相手に違約金を支払うといった内容を記載 |
| 契約不適合責任 | 契約不適合責任が発生する期間や欠陥の範囲などを記載 |
| 引渡し前の滅失・毀損 | 物件の滅失や毀損があった場合に、売り手や買い手がどのように対応するかを取り決めた内容を記載 |
| 反社会勢力の排除 | 買い手または売り手が反社会勢力の関係者だった場合、契約を解除できるという旨を記載 |
取引物件の表示
取引き物件の表示とは、不動産取引きの対象となる物件情報を記載する項目です。
- 所在地
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積 など
マンションの場合は、一棟の建物と専有部分の両方の記載が必要です。
一般的に使用される住所と登記上の所在地は、表記が異なるケースもあります。
そのため、契約書には登記簿謄本の情報をもとに記載されます。
売却代金・手付金の金額および支払い期日
不動産の取引きでは、売却代金を2回に分けて支払うのが一般的です。
先に手付金として売却代金の一部を支払い、後から残金を支払います。
契約書には、売却代金や手付金の金額が記載されています。
手付金の金額は、売却代金の5~10%程度が目安です。
契約書には手付金および売却代金の金額のほかに、それぞれの支払い期日も記載されています。
支払い期日は、契約書において重要な項目です。
期日を過ぎると契約違反になるため、その旨も記載する必要があります。
土地の実測および代金の清算
実際の土地と登記簿謄本に記載されている面積には、誤差が生じている可能性があります。
不動産取引においては土地の面積に誤差があることを想定し、売り手が費用を負担して実測を行うのが一般的です。
実測の結果、土地の面積に誤差がある場合は、差分を土地代金として清算します。
土地を実測し、差分を代金として清算する取引きは、実測売買と呼ばれています。
実測売買を行う場合、契約書にその内容の記載が必要です。
所有権移転および引渡し時期
複数の手続きをまとめて行うことを、同時履行と呼びます。
不動産の取引きにおいては、手付金を除いた売却代金の支払いと物件の引渡し、所有権の移転手続きは、同時に行われるケースがほとんどです。
同時履行が選択される理由は、物件を引渡したのに売却代金が支払われない、支払いを終えたのに物件が引渡されないといったトラブルを防ぐことが目的です。
そのため、契約書には所有権移転や物件の引渡し時期が記載されます。
付帯設備の引き継ぎ
不動産の取引きでは、建物内外の設備を売り手から買い手にどこまで引渡すかを明確にしなければなりません。
建物内外の設備には家電や家具だけでなく、敷地内に植えられた樹木も含まれます。
買い手に引き継がれた付帯設備は、物件の引渡し直後に不具合が起きる可能性があります。
そのため、物件の引渡しから一定期間内に発生した不具合は、売り手側に修復する責任があると契約書に明記するケースも珍しくありません。
また、契約書では撤去または処分する設備も明確にしておく必要があります。
負担の消除
賃借権や抵当権が設定された物件は、所有権を移転できません。
これらの権利が設定されたままで売買契約を進めることは、所有権の移転を阻害する行為になります。
そのため、不動産を売却する際には、賃借権や抵当権を抹消する手続きが必要です。
この手続きは、負担の消除と呼ばれています。
契約書には、物件の引渡しまでに権利を消除する旨の内容を記載します。
各種税金の清算
毎年1月1日時点の不動産の所有者は、固定資産税や都市計画税を1年分まとめて納税する義務があります。
1年の途中で不動産を取引した場合は、引渡し以降の税金を売り手が負担することになります。
そこで不動産取引では引渡し日を基準に税金を日割り計算し、売り手と買い手で清算するのが一般的です。
買い手は引渡し日以降の税金を実質的に負担し、不平等にならないよう調整します。
契約書には、売り手と買い手で税金をどの程度負担するかを記載します。
手付解除の期限
手付解除とは売買契約の締結から物件の引渡しまでの期間に、決められた金額を支払えば契約を解除できるというものです。
手付解除は、売り手と買い手のどちらからも申し出できます。買い手が申し出る場合は、一度支払った手付金を放棄することで解除できます。
一方で売り手側が申し出る場合は、買い手から受け取った手付金の2倍の金額を支払わなければなりません。
なお、売り手と買い手の双方が合意すれば、手付解除を認めない内容で契約することも可能です。
契約書には、手付解除の有効期限を記載します。
不動産売買の契約後の解除については下記の記事で詳しく解説しています。
契約違反による解除
契約違反による解除は、売り手と買い手のいずれかが契約違反をした場合、契約を白紙にできる旨を記載する項目です。
例えば売り手の過失により、引渡し前に物件が滅失または毀損すると、契約違反になります。
契約書では、違反した側が相手に違約金を支払うといった内容を記載するケースがほとんどです。
違約金の金額は、売却代金の20%までに設定されます。
違約金が支払われた後は、契約解除となります。
約不適合責任
不動産売買契約書には、契約不適合責任に関する内容を記載します。
契約不適合責任とは、物件の引渡し後から一定期間に何らかの欠陥が発覚した場合、売り手が責任を負うというものです。
例えば物件の引渡し直後に雨漏り箇所が見つかった場合、売り手が修繕に対応する必要があります。
契約不適合責任が発生する期間や欠陥の範囲などは、売り手と買い手で協議した上で取り決めます。
契約不適合責任については下記の記事で詳しく解説しています。
引渡し前の滅失・毀損
契約後の物件は、売り手と買い手のどちらにも責任が発生しない状態で、消滅したり損傷を受けたりする可能性があります。
例えば台風や地震などの自然災害によってダメージを受け、修復不可能になったケースです。
契約の解除権は売り手と買い手の双方にあるため、どちらも解除の申し出ができます。
契約解除に至った場合、売り手はすでに受け取った手付金を無利息で買い手に返還する必要があります。
一方の買い手は、売却代金の支払いを拒絶することが可能です。
契約書には物件の滅失や毀損があった場合に、売り手や買い手がどのように対応するかを取り決めた内容を記載します。
反社会勢力の排除
反社会勢力の排除は、買い手または売り手が反社会勢力の関係者だった場合、契約を解除できるという旨を記載する項目です。
すべての都道府県では暴力団排除条例が施行されており、契約を締結する際に暴力団排除条項を定めることを努力義務としています。
不動産取引きにおいては、次の内容を契約書に盛り込むことに努めなければなりません。
- 物件を反社会勢力の活動に利用しないこと
- 反社会勢力の活動に利用した場合は契約解除または売り手が買い戻せること
契約後に反社会勢力の関係者と発覚するリスクもあるため、契約書に記載しておく必要性があります。
不動産売買契約書に関するよくある質問

最後に、不動産売買契約書に関するよくある質問を紹介します。
土地売買契約書とは何が違うのか
不動産売買契約書と土地売買契約書は、契約対象が異なります。
不動産売買契約書の契約対象は土地と建物なのに対し、土地売買契約書は土地のみです。
戸建てやマンションを売買する場合は、不動産売買契約を用います。
どちらの契約書も、宅地建物取引業法の範囲内です。
そのため、契約書に記載される内容に大きな違いはありません。
不動産売買契約書は無料で作成してもらえるのか
不動産会社の仲介で取引きする場合、売買契約が成立すると仲介手数料が発生します。
仲介手数料とは不動産の売却活動を依頼した不動産会社に対し、売り手や買い手が成功報酬として支払う手数料です。
不動産売買契約書の作成費用は仲介手数料に含まれているため、別途費用を支払う必要はありません。
仲介手数料に関しては以下の記事で詳しく解説しています。
不動産売買契約書は印紙税の対象文書なのか
印紙税法で定められた文書に対しては、印紙税が課税されます。
不動産売買契約書は、印紙税の対象文書です。
不動産売買契約書は売り手分と買い手分の2通作成するため、2通分の印紙が必要です。
税率は、契約書に記載された金額によって異なります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
なお平成26年4月1日~令和6年3月31日までに作成された文書については、軽減税率が適用されます。
不動産売買契約書の内容は細部までチェックしよう

不動産売買契約書には、不動産の取引きに関する重要な取り決めが記載されています。
特に売却代金や物件の引渡し時期などの契約条件は、契約後にトラブルに発展するリスクがあるため、念入りに確認する必要があります。
契約書は契約内容を証明する書類になるため、契約後も大切に保管するようにしましょう。
万が一紛失した場合は、不動産会社や相手方に署名捺印をしてもらうことで、再発行が可能です。