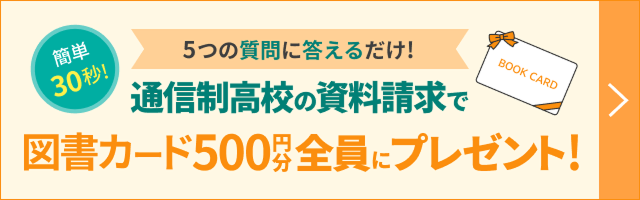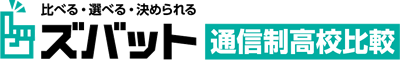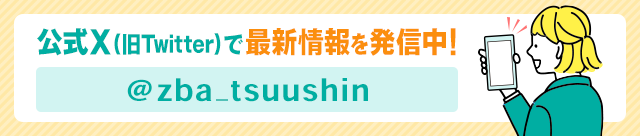不登校だと高校受験はどうなる?高校入試に向けた3つの対策
公開日:2018年02月09日 更新日:2025年03月04日
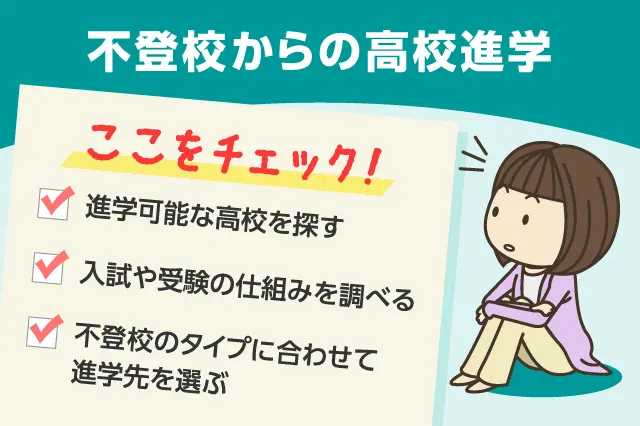
中学校に不登校の状況だと、「高校受験はどうなる?」「高校に行ける気がしない」と不安に思うこともあるでしょう。 不登校でも高校受験をすることは可能です。しかし、いくつか注意すべき点もあります。 この記事では、不登校の場合に高校受験で不利になるポイントや対策、タイプ別の志望校の選び方について解説します。
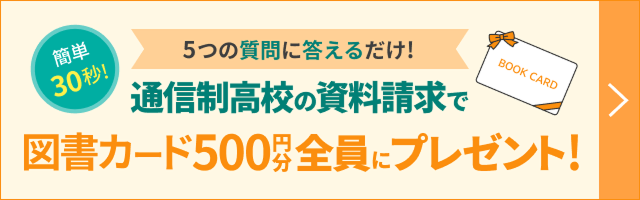
- 不登校から高校受験はできる!
- 調査書(内申書)とは?
- 不登校だと高校受験は不利になる?
- 不登校からの高校受験で焦らないための対策
- 不登校でも進学できる高校の種類
- 【不登校のタイプ別】志望校の選び方
- まとめ
不登校から高校受験はできる!
不登校の生徒でも高校受験・入試受けることは可能です。
日本の中学校は原則として年齢に基づく進級制度を採用しており、欠席日数が多い場合でも基本的には留年することはありません。そのため、不登校で出席日数が足りなくても進級・卒業が可能です。
ただし、高校によっては不登校が受験や進学で不利に働く場合もあるため注意しましょう。不登校から高校受験を目指す場合、学力試験以外に「調査書」の内容にも気をつける必要があります。
調査書(内申書)とは?
調査書(内申書)とは、中学校が生徒一人ひとりについて作成する成績や行動、学習態度についての記録で、高校入試の際に提出されます。
高校受験においては、学力試験だけでなく調査書の内容も加味される場合があるため、非常に重要です。
調査書の中でも、内申点と出欠状況は、高校受験の合否に影響する可能性があります。
内申点とは?
内申点とは、教科の成績を5段階で数値化したものです。対象となる教科は、国語・社会・数学・理科・英語・音楽・技術・美術・保健体育です。
テストの点数だけでなく、授業への参加態度、提出物の状況などが考慮され、9教科それぞれに5段階評価が付けられます。
内申点の取り扱いや計算方法は、都道府県によって異なります。
例えば、中学3年の成績のみを対象とする場合もあれば、全学年の成績を対象とする場合もあります。
また、中学3年の成績や実技教科の配点を高くするといった計算方法が採用される場合もあります。
なお、中学3年の学年末の成績は、内申点に含まれません。また、2学期制・3学期制で内申点に含まれる期間が異なります。
不登校だと高校受験は不利になる?
公立高校やの場合、調査書の内容を加味して合否を決定します。そのため、不登校の影響で内申点が低かったり、欠席日数が多かったりすると、受験で不利になる可能性があります。
一方、私立高校の一般入試においては、内申点や欠席日数は重視されない傾向があります。 ただし、推薦入試など、受験の形式によっては内申点や欠席日数が影響する場合もあります。
内申点の影響
不登校で定期試験が受けられないと、教科の成績が下がってしまいます。また、授業への出席や提出物の状況が影響するため、内申点が低くなってしまう可能性があるでしょう。
前述の通り、公立高校は内申点が合否判定に含まれます。ただし、都道府県や学校によって内申点が加味される比率が異なります。
例えば、東京都の公立高校の場合、学力試験と内申点の比率は原則「7:3」です。しかし、神奈川県では、学校によって「7:3」「6:4」「5:5」などさまざまです。
私立高校の一般入試では内申点は加味されませんが、推薦入試の場合は「5教科で20以上」「9教科で30以上」などの基準が設定されています。ほとんどの場合、中学3年の成績が対象となります。
欠席日数の影響
欠席日数は高校受験において重要な要素です。
公立高校の場合、欠席日数が多いと「審議の対象」となる場合があります。「審議の対象」とは、入試の結果が合格点に達していても、合否が審議されるということです。
基準は都道府県や高校によって異なり、「欠席日数が3年間で30日を超えると審議の対象となる」などの基準があります。
例えば東京都立高校の場合、欠席日数は合否に影響がありません。一方、1日欠席することで減点される学校や、皆勤の場合に加点される学校もあります。
また、欠席日数が多い場合は、自己申告書で理由を説明することで、配慮してもらえる場合もあります。
不登校からの高校受験で焦らないための対策
不登校から高校受験をする場合、内申点や欠席日数の観点で不利になる場合があります。
しかし、具体的な対策を講じることで、不利な状況を打開することは可能です。
教室に行かずに出席日数を増やす
欠席日数を増やさないための対策として、教室以外に「登校」する方法があります。例えば、保健室や別室など教室以外の場所に登校することで、出席と認めてもらえる場合があります。
学校に行くのが難しい場合は、「出席扱い制度」の利用も有効です。出席扱い制度は文部科学省が定める制度で、一定の条件を満たし、学校長が認めることで、登校しなくても出席扱いとして認められます。出席扱いとなる条件は、一律ではなく、当該生徒の状況に応じて判断されます。
フリースクールや教育支援センターに通うほか、ICT等を活用した自宅学習でも出席扱いになる場合があります。
不登校枠がある高校を探す
不登校枠とは、高校受験において不登校の生徒に配慮した選考方法です。不登校の生徒が不利にならないように、面接や自己PRシートを重視したり、欠席日数に代わる評価基準を設けたりするなど、特別な選考方法が用意されることがあります。
不登校枠の条件や選考方法については、都道府県や学校によって異なります。
不登校でも進学できる高校を探す
不登校の場合、選択肢は全日制高校だけではありません。通信制高校や定時制高校、不登校の生徒向けの全日制高校も選択肢に入ります。それぞれの学校には受験条件やカリキュラムの違いがあるため、自分に合った学校を見つけることが重要です。
不登校でも進学できる高校の種類
不登校であることを理由に「高校に行けない」ということはありませんが、受験で不利になる可能性があることは事実です。ここでは、不登校であることが受験に影響しにくい高校について解説します。
不登校でも行ける全日制高校
そもそも、中学で不登校だからといって、全日制高校に行けないということはありません。条件を満たせば、どの高校でも受け入れてもらえます。
ただし、公立高校の場合、内申点や欠席日数の関係で、受験が不利になる可能性があります。
不登校から全日制高校を受験する場合、私立高校や不登校枠のある公立高校を選べば、不登校の影響を受けにくいと言えます。
不登校や中退者向けの高校
不登校や中退者向けの高校に通うのも、選択肢の1つです。
例えば、東京都の場合、チャレンジスクールが該当します。チャレンジスクールは、小・中学校での不登校経験者や高校中退者を対象としており、能力や適性を発揮できなかった生徒を支援することを目的とした高校です。
チャレンジスクールの入試では、学力試験を実施せず、調査書(内申書)も使用しないため、不登校であることが不利に働くことはありません。
都道府県によって呼び名や対象者が異なり、神奈川県のクリエイティブスクール、大阪府のエンパワーメントスクールなどがあります。
定時制高校
定時制高校を受験するには、調査書(内申書)の提出が求められます。ただし、定時制高校は社会人など幅広い年齢層からの入学希望者を受け入れているため、内申点が合否に影響を及ぼすことはほとんどありません。
また、定時制高校の入試は、学力よりも意欲や学びたいという気持ちを重視する傾向があるため、不登校で学力に不安があっても、全日制高校と比べると合格しやすいと言えるでしょう。
通信制高校
通信制高校の入学試験では、内申書の内容が合否に影響することはほとんどありません。
また、試験内容も面接や作文のみの場合が多く、学力試験が課されることはほとんどありません。
通信制高校の入学試験は、「落とすこと」を目的としていないため、合格率が高いのも特徴です。
人間関係にストレスを感じて不登校になってしまった場合、自宅で学習を進めることができる通信制高校は、有効な選択肢になるでしょう。
なお、通信制高校については、『通信制高校とは?カリキュラムや全日制との違いをわかりやすく解説』も参考にしてください。
【不登校のタイプ別】志望校の選び方
高校受験の志望校選択においては、内申点や出欠状況が重要な要素となります。
何学年までを調査書の対象とするかが、都道府県や学校によって異なるため、状況に応じた志望校選びが重要です。
不登校だったが今(中3)は学校に行っている場合
中学1年や2年の内申点や出欠も対象となる学校の場合、受験に不利な影響が出る可能性があります。
中学3年の内申点を重視する都道府県や学校を選択すれば、特に問題はありません。
中3の時点で不登校の場合
内申書の提出が必要な高校の場合、中学3年時点の内申点や出席日数は必ず評価の対象になります。
そのため、中学3年で不登校の場合、調査書を重視しない私立の全日制高校や、定時制高校なども選択肢に加えると良いでしょう。
不登校が長期間にわたる場合、全日制高校に通っても、集団生活になじめない可能性もあります。その場合は、通信制高校も視野に入れて検討することをおすすめします。
また、不登校枠がある高校を受験するのも有効です。
まとめ
不登校でも高校受験は可能です。ただし、不登校の場合、内申点や出席日数の点で、受験が不利になる可能性があります。
しかし、出席扱い制度を利用したり、不登校枠のある高校や調査書を重視しない高校を受験したりすることで、対策することも可能です。
不登校が高校受験に与える影響を理解し、落ち着いて対策するようにしましょう。