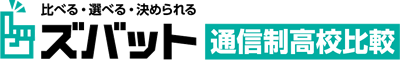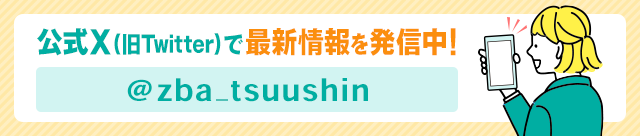子供が「高校を辞めたい」と言ってきたら親はどう対応すべき?
公開日:2018年02月14日 更新日:2025年03月31日
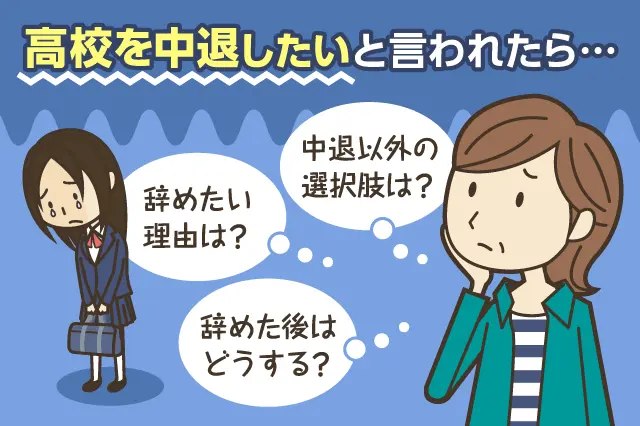
子どもから「高校を辞めたい」「退学したい」と言われたとき、親としてどのように対応すべきか戸惑うことでしょう。このような状況では、お子さんの気持ちを理解し、将来を見据えたサポートが求められます。この記事では、親が取るべき最初の対応から、高校を辞めたい理由の背景、そして中退以外の選択肢まで詳しく解説します。お子さんに寄り添いながら最適な道を一緒に見つけるためのヒントをお届けします。
「高校を辞めたい」と言われたときの最初の対応
子どもが高校辞めると言い出したとき、驚きや不安で心が揺れることでしょう。この状況では、感情的にならず冷静に対処することが求められます。
子どもの気持ちを理解し、適切なサポートを提供するための最初の一歩を踏み出しましょう。
子どもの思いをじっくり聞く
まずは理由をといただすのではなく、お子さんの気持ちを受け止め、じっくりと話を聞くことが大切です。
子どもが感じている悩みや苦しみを理解しようとする姿勢を示すことで、信頼関係が築け、真の理由に近づくことができます。感情的にならず、共感するような態度で接することで、お子さんも心を開きやすくなります。
辞めたい理由を冷静に確認する
話を聞く中で、息子さんや娘さんが高校を中退したいと感じる具体的な理由を冷静に確認しましょう。人間関係の悩みや学業の困難、将来の進路に対する不安など、背景にはさまざまな要因があるかもしれません。
焦らずに質問し、子どもの言葉を尊重しながら、本音を引き出す努力が求められます。理由を正確に把握することで、適切なサポート方法を見つける手がかりとなります。
将来への影響を一緒に考える
お子さんの気持ちを受け止めた上で、高校を辞めることが将来にどのような影響を及ぼすのか、一緒に考える時間を持ちましょう。
感情的な説教ではなく、事実に基づいた情報を共有し、選択肢や可能性について話し合います。お子さん自身が自分の将来を見据えた判断ができるよう、サポートする姿勢が大切です。
高校を辞めたいと思う理由とその背景
お子さんが高校を辞めたいと感じる背景には、さまざまな理由があります。その原因を理解することで、適切な支援や解決策を見つける手助けとなります。
文部科学省のデータを見ると、退学の理由にどんなものがあるかがわかります。
| 退学事由 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 学業不振 | 3,124人 | 6.8% |
| 学校生活・学業不適応 | 15,804人 | 34.2% |
| 進路変更 | 19,087人 | 41.3% |
| 病気けが死亡 | 1,971人 | 4.3% |
| 経済的理由 | 567人 | 1.2% |
| 家庭の事情 | 1,333人 | 2.9% |
| 問題行動等 | 1,527人 | 3.3% |
| その他 | 2,825人 | 6.1% |
※文部科学省初等中等教育局児童生徒課「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」
人間関係が原因となるケース
高校生活において、友人やクラスメイトとの人間関係は大きな影響を及ぼします。いじめや仲間外れ、教師との摩擦など、人間関係の悩みが原因で学校に行くことが辛くなるケースは少なくありません。
お子さんが感じている孤立感やストレスに気づき、適切な対処をすることが必要です。場合によっては、学校や専門機関と連携して問題解決に努めましょう。
勉強や授業についていけない問題
学業面でのつまずきも、高校を辞めたいと感じる大きな要因です。授業内容が難しく理解できない、成績が思うように伸びないといった挫折感が、お子さんの自信を喪失させることがあります。
このような場合、学習方法を見直したり、家庭でサポートしたりすることで、状況が改善する可能性があります。早めの対応が継続の鍵となります。
本人の将来や進路に対する葛藤
お子さん自身が将来の目標や進路について悩み、高校生活に意義を見いだせなくなることもあります。自分が本当にやりたいことが他にある、現在の進路が合わないと感じているのかもしれません。
こうした葛藤に対し、親としてはお子さんの希望や興味を尊重し、多様な進路について情報提供を行うことが重要です。新たな目標設定が、モチベーションの回復に繋がることもあります。
高校中退の影響を理解する
高校を中退することが、お子さんの将来にどのような影響を与えるのかを親として正しく理解することは重要です。その上で、最善のサポートを提供できるよう準備しましょう。
進学への影響
高校中退は、大学や専門学校への進学に大きな影響を及ぼします。大学や専門学校を受験するには高卒資格が条件となっています。
高校を辞めると進学の道を閉ざしてしまう可能性があるため、お子さんの将来の選択肢が大きく制限されることになります。
就職への影響
就職面でも、高卒資格がないことで応募できる職種や企業が限られてしまいます。多くの企業が採用条件として高卒以上を求めており、中退者は選択肢が狭まります。
また、学歴が採用後の給与や昇進に影響を与えるケースもあります。将来的なキャリア形成において、不利な状況に立たされる可能性があります。
社会的な偏見
高校中退に対する社会的な偏見や誤解も存在します。中退者は「忍耐力がない」「問題がある」といったネガティブなイメージを持たれがちです。
お子さんがそのような偏見にさらされ、自尊心を傷つけられることも懸念されます。親として、そのような社会的な偏見からお子さんを守り、支える姿勢が求められます。
子どもと一緒に進路を考える際の注意点
お子さんの気持ちを尊重し、共に進路を考える姿勢が求められます。親としてのサポートが、お子さんの将来に大きな影響を与えることを念頭に置きましょう。
子どもに寄り添い応援する
お子さんが困難に直面しているとき、親が寄り添い応援する姿勢を示すことは重要です。批判や強制ではなく、理解と共感を持って接することで、お子さんは安心して自分の気持ちや考えを表現できます。
親のサポートは、お子さんの自己肯定感を高め、前向きな行動につなげる力となります。信頼関係を築きながら、一緒に最適な道を探していきましょう。
早急に結論を出さない
焦って結論を急ぐと、お子さんにとって最良の選択を見逃す可能性があります。時間をかけて情報を集め、さまざまな選択肢を比較検討することが大切です。
お子さん自身も気持ちの整理がつきやすくなり、主体的に将来を考える機会となります。ゆとりを持った話し合いは、親子双方にとって納得のいく決断に繋がります。
担任の先生や専門家へ相談する
学校の担任やカウンセラー、教育相談機関などの専門家に相談することで、新たな視点や有益な情報を得られることがあります。第三者の意見は、お子さんの状況を客観的に理解する助けとなります。
また、専門家は進路変更や学業継続に関する具体的なアドバイスや支援策を提案してくれます。
親の希望や価値観を押し付けない
親として、自分の経験や価値観をもとにお子さんにアドバイスをしたくなるのは自然なことです。しかし、それが押し付けになってしまうと、お子さんの自主性や意思決定を阻害する可能性があります。
お子さんは自分の人生を生きており、自分自身の考えや感じ方があります。親の意見を伝える際も、お子さんの気持ちや考えを尊重し、対話を通じて理解し合うことが重要です。
通信制高校への転校も選択肢
高校を辞める以外にも、お子さんが学業を続けられる選択肢は多く存在します。特に通信制高校は編入・転入先としておすすめです。新たな環境で再スタートを切ることも視野に入れましょう。
通信制高校とはどのような学校か
通信制高校は、自宅学習を中心に高卒資格を取得できる教育機関です。
スクーリング(面接指導)やレポート提出、試験を通じて単位を修得します。自分のペースで学習を進められるため、学校生活に困難を感じているお子さんにとって有効な選択肢となり得ます。
多様なカリキュラムやサポート体制を持つ学校も増えており、興味や適性に合わせて選ぶことができます。
通信制高校について詳しくは、『通信制高校とは?カリキュラムや全日制との違いをわかりやすく解説!』も参考にしてください。
在籍する学校から転校や転入する手続き
現在の学校から通信制高校に転入・編入する際には、所定の手続きが必要です。まず、転校先の学校の入学要件や募集時期を確認しましょう。
その後、在籍校での退学手続きや、取得済みの単位の引き継ぎについて相談します。
手続きには時間がかかる場合もあるため、早めの行動が望まれます。学校や教育委員会の窓口で詳しい情報を得ることができます。
通信制高校への転入・編入については、『通信制高校への編入と転入の違いを解説!注意点から判断ポイントまで紹介』も参考にしてください。
『自分に合う通信制高校がわからない』『おすすめの学校を提案してほしい!』
そんな声にお応えして、【通信制高校診断】をご用意しました。60秒で診断完了できます!
まとめ
お子さんが高校を辞めたいと告げたとき、まずはお子さんの気持ちに寄り添い、じっくりと話を聞くことが大切です。辞めたい理由や背景を理解し、将来への影響や可能性について一緒に考える時間を持ちましょう。
通信制高校など、学び続けるための選択肢はさまざまです。焦らずに情報を集め、専門家の意見も参考にしながら、お子さんにとって最適な進路を見つけてください。
高校を中退した場合にどうなるのか気になるという人は、『高校を中退したらどうなる?その後の影響や選択肢を解説』も参考にしてください。