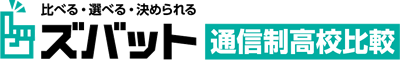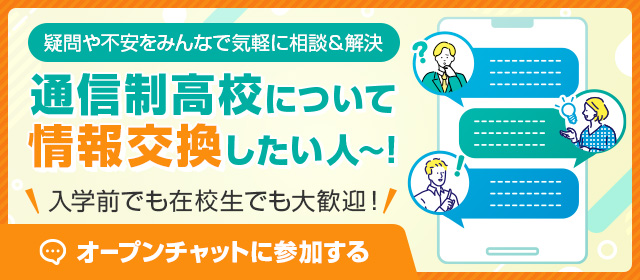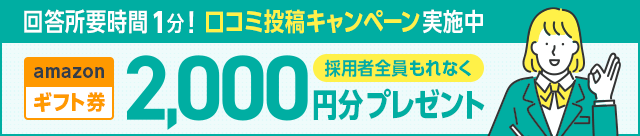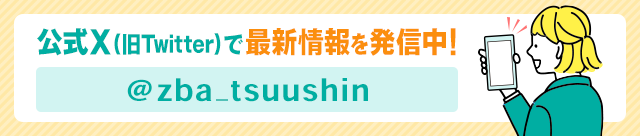「学校に行きたくない」中学生の保護者としてどのようにサポートすべき?行きたくない理由や対処法を解説
公開日:2021年09月13日 更新日:2024年02月28日
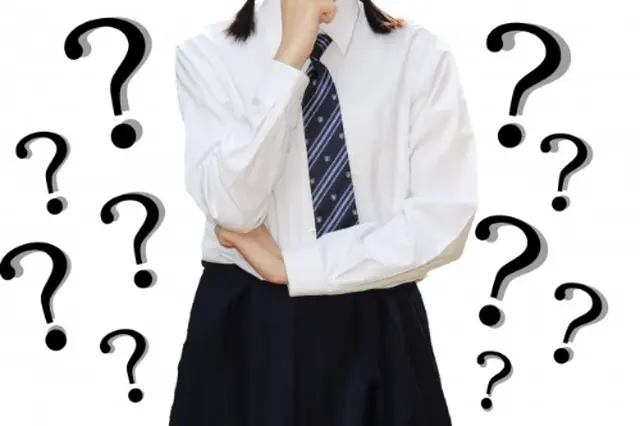
中学生の子供から突然「学校に行きたくない」と言われたら、戸惑わない保護者はいないでしょう。子供にとって学校は日常の一部。よほどの理由がなければ「行きたくない」という声を発することはないはずで、保護者に助けを求めていることは間違いありません。この記事では、中学生が「学校に行きたくない」と訴える理由や、保護者ができること、対応における注意点などをを解説します。
- 「学校に行きたくない」は子供からのサイン
- 学校に行きたくないという理由にはどのようなものがある?
- 勇気を出して「学校に行きたくない」と言った子供に寄り添うために
- 学校を休んでいるあいだにやっておくと良いこと5つ
- 「学校に行きたくない」に対して保護者ができること
- 子供の「学校に行きたくない」という声にしっかり向き合おう
「学校に行きたくない」は子供からのサイン
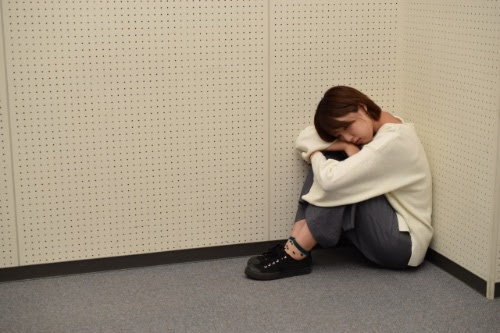
子供の「学校に行きたくない」という発言は、保護者にとっては衝撃の一言なのではないでしょうか。子供にとっても、勇気のいる発言だったでしょう。そんな子供からの「緊急サイン」を、どのように受け止めればよいのでしょうか。まずは、子どもの身の回りにどのような変化が起きているのかを考えてみましょう。
中学校の環境や、自分自身の変化に対応できないことがある
中学生になると、小学校とはさまざまな点が変わります。教科ごとに異なる先生、授業の内容や難易度、部活動での先輩後輩を含めた人間関係など、未知の出来事に触れる機会が急激に増えます。
さらに、思春期を迎えることで自身の身体や心にも変化が現れます。何かと保護者に反発したり、急に怒り出したり、これまでとはまったく違う様子に驚くかもしれません。しかし、実は子供自身も戸惑っているのです。
むしろ、自分だけでこの変化に対処するほうが難しいと言えるでしょう。考えてもどうすればいいのかわからず、それでも「自分でなんとかしないと」と焦り、かえって悩みが深くなってしまうこともあります。それほど真剣に悩んでいるのです。
大人にとっては取るに足らない悩みかもしれませんが、子供にとってはたいへん深刻な問題です。もしかすると、家族に言えない悩みを抱えているかもしれません。放置し続ければ、体調や感情をうまくコントロールできないことで成績や人間関係にも影響する可能性があります。
保護者としては、子供と一緒にこの難局をうまく乗り切るため、上手にサポートすることが重要です。
学校に行きたくないという理由にはどのようなものがある?

中学生の「学校に行きたくない」理由はひと括りにはできませんが、多いものをいくつか紹介します。
(1)人間関係の変化にうまく対応できない
中学生になると、行動範囲や交友範囲が広くなります。その中で人間関係が変化し、友達同士でも、以前は仲が良かったのに同じグループに入れなかったり、孤立してしまったりする場合もあるでしょう。また部活動などを通じてこれまで知らなかった人間関係や礼儀、ルールにも直面するでしょう。急激な変化についていけないのも当然です。
スマートフォンの普及によって、学校以外でも四六時中コミュニケーションが発生し、学校の人間関係から完全に解放されることがないため、疲れてしまう場合もあるでしょう。
このような人間関係の変化に試行錯誤しながらも対応することは、まだ未成熟な中学生にとって大変なことです。疲れ果ててしまい、「ちょっと休ませて」という意味で学校に行きたくないと訴えるのは、仕方がないことなのかもしれません。
(2)授業のペースについていけない
小学校では原則としてすべての科目を担任の先生が教えますが、中学校では教科ごとに先生が変わる教科担任制なので、科目によって授業の進むペースや教え方も異なります。内容も難しくなるため、授業についていけなかったり、内容が理解できないまま置いていかれてしまったりということが起こりやすいでしょう。
また、数学や英語のように、前の授業内容が理解できていないと次の内容が理解できないという科目もあります。わかるところまで戻って復習できればいいのですが、そもそもペースが早いので復習の時間まで確保できず、どんどんついていけなくなってしまうという状況に陥りがちです。
(3)親子・きょうだい関係が変化した
例えば、保護者から「もう中学生になったんだから、自分でなんとかしなさい」「お兄ちゃん・お姉ちゃんなんだから我慢して」などと言われるようになったら、子供はどう感じるでしょうか。頭の中や理屈ではわかっていても、どこか寂しい、悲しい気持ちになることもあるでしょう。
ほかにも、何かにつけてきょうだいと比べられたり、態度が厳しすぎたり、無関心だったりと家族間のコミュニケーションに問題があれば、やはり精神的に疲れてしまうかもしれません。
学校生活も大変なのに、家庭でも心が休まらなければ、疲れ果ててしまうのも当然です。このような状態が続くと、最悪の場合、うつ病を発症してしまうこともあります。
勇気を出して「学校に行きたくない」と言った子供に寄り添うために
子供は、「学校に行きたくないと言ったら、親から何と言われるだろう」と考えています。「ずる休み」「怠け者」などと叱られるのではないか、と考えるからこそ「学校に行きたくない」と言えず、我慢が蓄積してしまうのです。
そのため、子供の訴えをネガティブに考えるのではなく、「それなりの理由があるはずだ」「自分だけではどうしようもないから勇気を持って口に出したのだ」と捉え、まずは耳を傾けてあげましょう。例えば「疲れているならまずは休もう」「一緒に考えたいので話してほしい」などと伝え、子供に寄り添う態度を示しましょう。子供にとって、それはきっと大きなよりどころとなるはずです。
勇気を出して「学校に行きたくない」と言えた子供の気持ちをしっかり受け止めるためにも、いざというときにどのような受け答えをするべきか、心構えはしておきたいものです。
学校を休んでいるあいだにやっておくと良いこと5つ

ここでは、学校を休んでいるあいだにやっておくと良い、おすすめの行動を5つ紹介します。
まずはゆっくり休息する
「冷静に考えることができない」「体が疲れている」などと感じたら、まずは心身が回復するまで思う存分、ゆっくり休むことをおすすめします。1日中横になって何もしなかったり、昼夜逆転したりするかもしれませんが、それでも心にゆとりができるまで無理をする必要はありません。休まずに疲れが残ったまま焦って行動すると、さらに不調が続いてしまう恐れがあります。
家族と話すことで自分と向き合う
もし子供の心に余裕があれば、思っていることを正直に話してもらいましょう。うまく話せなかったり、途中でわからなくなったりするかもしれませんが、それでも構いません。ゆっくり落ち着いて、しっかり向き合って話すことで、多少なりともつらさが軽減されたり、気持ちが落ち着いたりするはずです。
わかるところから勉強を進める
授業内容がよくわからず、わかるところまで戻って復習したいなら、この機会に苦手なところを勉強するのもいいでしょう。将来的に進学するにしろ、就職するにしろ、努力できるという自信や身についた学力はきっと役立ちます。
高校進学を考えているなら、通信制高校を検討してみる
高校進学を見据えているのであれば、体調や人間関係に不安がある人にとって全日制高校は少々ハードルが高いと感じるかもしれません。全日制高校は出席日数が少ないと進級・進学が難しいため、通学日数を問わない通信制高校のほうがおすすめです。
通信制高校は、全日制の高校とはカリキュラムや学習方針が違う学校が多くあります。自分に合った通学日数を選べるため、週1日や月2日だけの登校で済むケースも。
また、最近では個別学習できる通信制高校も増えています。必要に応じて中学生の習う単元を復習するなど、基礎的な学力がつくカリキュラムを充実させている学校も多数あります。そんな学校なら、学力に不安があっても大学進学や就職の具体的な道も見えてくるはずです。
「ズバット 通信制高校比較」では、さまざまな条件から自分に合った学校が選べるコンテンツを用意しています。最小限の通学日数で卒業を目指せる学校や、興味があることや好きなことに特化して学べる学校など、さまざまな通信制高校を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
>>あなたに合う通信制高校診断
>>【ジャンル別】人気の通信制高校まとめ
家族以外の相談先を探すのも選択肢のひとつ
学校に行きたくない理由を子供がどうしても打ち明けたがらない、というケースもあるかもしれません。そんなときには、家族とは別の相談先に助けを求めるという方法もあります。
- スクールカウンセラー:学校にいる生徒からの相談を受けてくれる専門家
- 教育相談センター:都道府県など自治体が運営し、直接訪問や電話、メールで相談できる
- ひきこもり地域支援センター:都道府県や指定都市に設置された、ひきこもりに特化した相談窓口で、臨床心理士や社会福祉士などの専門家に相談できる
- 子供の人権110番:不登校やいじめ、親からの虐待など子供が関係するさまざまな問題を解決するための相談窓口
相談先を変えるだけで、意外なほど冷静に考えがまとまるときもあります。身近に相談相手がいなくても、このような相談先があることは覚えておきましょう。
「学校に行きたくない」に対して保護者ができること

保護者は子供が大切だからこそ、「勇気を持ってほしい」「負けないでほしい」と思うものです。しかしときにはその激励が、子供にとって苦痛になることを知る必要があるでしょう。ここでは、保護者ができることを3つ紹介します。
感情的に叱ったり責めたりしない
育った世代が子供とは違う、ということは、子供に接するときの前提として頭に入れておきましょう。親が中学生だったときとは、社会の状況はまったく違います。子供に「自分が中学生だったころは…」などと話しても理解できず、かえって反発を招くことにもなりかねません。
ましてや感情的に精神論を唱え、叱ったり責めたりするのは避けたいものです。子供が勇気を出して声を上げたにもかかわらず、「やっぱりわかってもらえない」と事態を悪化させてしまう可能性さえあります。
話をするより「傾聴」に徹する
子供にとって保護者の言葉は、保護者が思う以上に「重い」と意識することも大切です。保護者はなにげなくアドバイスしたことも、子供が「命令」のように受け取り、プレッシャーとなって子供を苦しめてしまうこともありえます。保護者からも意見を言いたくなりますが、まずは子供の悩みや考えを聞くことが重要です。
子供が話せないときは話せるまで待ち、話し始めたら親の考えを挟まず、じっくり「聞くに徹する」ことが大切です。適度にあいづちを打ち、「ちゃんと聞いているよ」「ゆっくりでいいよ」と示すと、より話しやすくなります。
子供の将来に必要な情報はあらかじめ調べておく
子供がこれからどう生きていくか、進学や就職をどうしてほしいのか、親としての願いや思惑もあるでしょう。もちろん子供自身でも調べられるかもしれませんが、情報の探し方は保護者のほうがずっとわかっているはずです。子供の将来にまつわる情報は、保護者も積極的に集めておき、必要なときにアシストできるようにしておきましょう。
子供の「学校に行きたくない」という声にしっかり向き合おう

中学生になったとはいえ、親にとってはまだまだ子供かもしれません。しかし子供は子供なりに、さまざまなことを真剣に考え、悩んでいます。「学校に行きたくない」という言葉も、安易に「ずる休み」「怠け者」などと片付けてしまわず、真剣な訴えとしてしっかり向き合いたいものです。まずは子供が置かれている状況を把握し、心身を休ませ、必要なサポートができるように慎重に対応していきましょう。
『本人に合う通信制高校がわからない』『おすすめの学校を提案してほしい!』
そんな声にお応えして、【通信制高校診断】をご用意しました。60秒で診断完了できます!