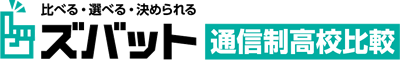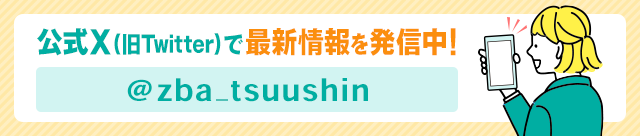不登校から目指す高校入学と大学進学

不登校のときは、将来のことがわからず、不安に思うかもしれません。しかし、不登校でも高校や大学への進学は可能です。大事なのは、不登校から学校へ復帰して、進路を選ぶこと。不登校からの進学で知っておきたい、基礎知識を紹介します。
-
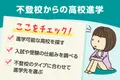 不登校だと高校受験はどうなる?高校入試に向けた3つの対策
不登校だと高校受験はどうなる?高校入試に向けた3つの対策
中学校に不登校の状況だと、「高校受験はどうなる?」「高校に行ける気がしない」と不安に思うこともあるでしょう。 不登校でも高校受験をすることは可能です。しかし、いくつか注意すべき点もあります。 この記事では、不登校の場合に高校受験で不利になるポイントや対策、タイプ別の志望校の選び方について解説します。
-
 不登校の子供を支援する『教育機会確保法』とは?
不登校の子供を支援する『教育機会確保法』とは?
不登校の児童、生徒たちを支援する法案『教育機会確保法』が、2017年2月より施行されました。それ以降、不登校やフリースクールに関して行政をはじめ関係組織による話し合いや試行錯誤が繰り返されています。
-
 フリースクールとは?費用や活動内容、不登校特例校との違いを徹底解説
フリースクールとは?費用や活動内容、不登校特例校との違いを徹底解説
フリースクールとは、不登校の生徒や学校に適応できない子どもたちに、多様な学びの場を提供する教育施設です。 不登校の小中学生が増加する中、学校に行けない子どもたちの居場所として、注目を集めています。 この記事では、フリースクールの概要や費用、具体的な活動内容、不登校特例校との違いなどについて解説します。
-
 不登校の高校生への対応は?原因・対策・進路まで徹底解説
不登校の高校生への対応は?原因・対策・進路まで徹底解説
不登校の高校生を抱える親にとって、子どもにどのように対応すれば良いのかは悩みとなります。小学校や中学校と異なり、高校の場合、不登校を放置すると、進学や就職などの進路に影響が出る可能性があります。この記事では、高校生の不登校の原因や進路への影響を解説し、NG行動や具体的な対策を紹介します。
-
 不登校の原因は何がある?原因不明でやってはいけないことも解説!
不登校の原因は何がある?原因不明でやってはいけないことも解説!
子どもが不登校になった場合、親としては、できるだけすぐに原因を明らかにして問題を解決し、少しでも早く学校に行けるようになって欲しいと願います。しかし、不登校の原因は複雑で、学校生活、人間関係、家庭環境、心身の問題などさまざまな要因が絡んでいます。この記事では、不登校の主な原因を解説し、それぞれの原因に対する具体的な対処法を紹介します。
-
 不登校だと将来どうなる?進学や就職の選択肢は?
不登校だと将来どうなる?進学や就職の選択肢は?
不登校が長期化して、子供の将来を心配する親も少なくありません。実際のところ、進学や就職にどんな影響があるのか、気になる人もいるでしょう。この記事では、不登校の子供の将来的なリスクと、進路選択について解説します。
-
 不登校中の勉強法は?子どもが勉強しない理由や対応を解説
不登校中の勉強法は?子どもが勉強しない理由や対応を解説
子どもが不登校になると親はさまざまな不安を抱きます。「子どもが勉強をしなくなってしまった」「このままだと勉強が遅れるのでは」など、子どもの学習面に不安を抱えている保護者もいるでしょう。この記事では、中学生で不登校の子どもが勉強しなくなる理由や対応方法、不登校の子どもの勉強方法について解説します。
-
 不登校を克服するには?不登校のきっかけや親や周囲にできること
不登校を克服するには?不登校のきっかけや親や周囲にできること
子供が学校に行かない、または行けなくなった場合、ほとんどの家族や周囲の大人は一日も早く不登校を克服してほしいと願うのではないでしょうか。また、子供が不登校を克服するためには、どうすればよいのだろうと悩む方も多いことでしょう。 不登校になった原因がさまざまであるように、不登校を克服するきっかけも多様です。また、この原因にはこの方法が効果的といった正解もありません。しかし、どのようなきっかけで不登校を克服できたのか、これまでの事例を知ることで解決の糸口が見つかる可能性もあります。 この記事では、子供が不登校を克服するきっかけとなった例や、親や周囲が不登校克服のためにできることなどについて詳しく解説します。不登校克服のきっかけが見つからなくて困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
-
 不登校からの復帰を目指す!保護者の心構えや意識するポイントを紹介
不登校からの復帰を目指す!保護者の心構えや意識するポイントを紹介
不登校から復帰を目指すためには、子供自身が前向きになっていることが重要です。子供が前向きになるためには、保護者の理解あるサポートが欠かせません。 本記事では不登校の子供と接する保護者の心構えや意識するポイントについて紹介します。保護者の何気ない一言や日頃の接し方は子供に大きく影響するものです。 日頃のやり取りを思い返しながら、読み進めていただければと思います。
-
 不登校の回復期は焦らず見守りを。回復のサインをキャッチしよう
不登校の回復期は焦らず見守りを。回復のサインをキャッチしよう
不登校は、学齢期の子供にとって大きな問題となっています。その数は年々増加しており、また不登校の長期化も課題のひとつです。しかし、子供はずっと不登校でいたいわけではありません。「そろそろ学校に復帰したいな」と、回復の兆候を見せるタイミングが訪れます。そのタイミングを見極め、適切な段階を踏むことで、子供は自ら不登校を抜け出すことができるでしょう。今回は、不登校から回復する段階と、親や周りの大人の関わり方などについて紹介します。
-
 小学生で不登校になる原因は?親のNG対応や解決方法を解説!
小学生で不登校になる原因は?親のNG対応や解決方法を解説!
小学生の不登校は、かつてないほど増加傾向にあります。文部科学省の令和5年度調査では、小・中学生あわせて34万6,482人が不登校に該当しており、過去最多となりました。とくに小学生の不登校割合は2.1%にのぼり、例えば学年に3クラスある学校なら学年に1人以上が不登校という計算になります。この記事では、不登校の現状や原因、親が注意すべき対応について解説します。
-
 学校に行きたくないときの対処法とは?NG行動や相談先も紹介
学校に行きたくないときの対処法とは?NG行動や相談先も紹介
学校に行きたくないと悩む子どもをもつ保護者の中には、「このまま不登校になってしまうのではないか」「将来に影響するのではないか」と不安を抱える人もいるでしょう。 子どもが学校に行きたくないと思う背景には、学業の悩みや人間関係の不安などさまざまな理由があります。そのため、子どもの意思を尊重して慎重に解決策を見つけることが大切です。 この記事では、子どもが学校に行きたくないと感じる理由やその対処法、避けるべき行動などを解説しているので、ぜひ参考にしてください。
-
 中学で不登校でも高校進学を諦めない!通信制高校という選択肢のメリットは?
中学で不登校でも高校進学を諦めない!通信制高校という選択肢のメリットは?
不登校の中学生を持つ親にとって、「不登校だと高校進学ができないのではないか」という不安は大きいでしょう。しかし、中学校で不登校だからと言って高校に行けないということはありません。 中でも通信制高校は、全日制高校とは異なる学びの形態を提供しており、不登校経験がある生徒にとって学習しやすい環境が整っています。 この記事では、通信制高校の卒業要件や入学試験、メリットやおすすめの人について解説します。
-
 怠け者タイプ(無気力型)の不登校|注意点や効果的な対処法は?
怠け者タイプ(無気力型)の不登校|注意点や効果的な対処法は?
怠け者タイプ(無気力型)の不登校児は、精神的には落ち着いている一方で、学校に行くのが面倒くさいと感じる傾向にあります。その原因が不明確なことも多いです。この記事では、怠け者タイプの不登校児の特徴や、効果的な対処法を解説します。
-
 不登校とは|文科省は年間30日以上の欠席を不登校と定義。ひきこもりとの違いも解説
不登校とは|文科省は年間30日以上の欠席を不登校と定義。ひきこもりとの違いも解説
文部科学省では、不登校の定義を「年間30日以上の欠席」としています。この記事では、不登校の原因やひきこもりとの違いについて解説します。さらには、不登校の原因や具体的な対処法に関しても紹介していきます。不登校に関する悩みを抱えている人は、ぜひ参考にしてください。
-
 不登校の高校生が転校するタイミングは?転校のメリット・デメリットを解説
不登校の高校生が転校するタイミングは?転校のメリット・デメリットを解説
不登校の問題に直面していて、転校を検討している人もいるでしょう。引っ越しをしないと転校できないと思うかもしれませんが、それ以外の理由でも転校をすることは可能です。 しかし、不登校の原因はさまざまです。学校環境の変化や新しい関係作りが解決の糸口となることもありますが、慎重な判断が必要です。 この記事では、高校で不登校を理由に転校する場合のメリット・デメリット、具体的な転校先の選び方について詳しく解説します。
-
 夏休み明け不登校になったらどうする?原因と対処法を解説
夏休み明け不登校になったらどうする?原因と対処法を解説
夏休み明けに急に学校に行けなくなってしまう生徒は少なくありません。朝起きられない、教室に入れない、友達と話せない――不安は本人も家族も深刻です。まずは責めずに「今できること」を確認しましょう。この記事では、夏休み明けに不登校になりやすい原因、家庭や学校での具体的な対応について解説します。
-
 不登校は10タイプに分けられる!それぞれの対応方法も解説
不登校は10タイプに分けられる!それぞれの対応方法も解説
子どもの不登校問題に悩む親にとって、不登校の原因と対応方法を理解することは重要です。この記事では、子どもが不登校になる10のタイプを詳しく解説し、それぞれのタイプに対する具体的な対応方法を紹介します。
-
 通信制高校に行きたいけど親の気持ちが気になる。どうやって伝えればいい?
通信制高校に行きたいけど親の気持ちが気になる。どうやって伝えればいい?
通信制高校への進学を考えているけれど、親がどう思うかが気になる中学生もいるでしょう。 通信制高校は、近年入学者数が増加していますが、「通信制高校は不安」と感じる親もいるかもしれません。 この記事では、通信制高校に行きたいと思ったとき、親にどのように話すべきか、具体的なアドバイスを提供します。
-
 不登校中にゲームばかり。取り上げてはいけない理由とは
不登校中にゲームばかり。取り上げてはいけない理由とは
中学生が不登校になる要因はさまざまですが、ゲームと不登校には関係があるのでしょうか。 文部科学省の調査によると、不登校の中学生が「最初に学校に行きづらいと感じたきっかけ」については、「インターネット、ゲーム、動画視聴、SNS」が17.3%という結果でした。 また、不登校の中学生の80%以上が、家でゲームやインターネットをしていたと回答しています。 このように、不登校とゲームの関係は、切り離すことのできない課題であり、適切に対処しなければ、ゲーム依存症になってしまうリスクもあります。 この記事では、不登校中の子どもがゲームばかりしている場合に、無理やり取り上げてはいけない理由や、どう対処すべきかについて解説します。
-
 高校生が学校に行きたくない理由は?親はどう対応すべき?
高校生が学校に行きたくない理由は?親はどう対応すべき?
学校に行きたくないと悩む高校生を持つ保護者の中には、「このまま不登校になってしまうのではないか」「将来に影響するのではないか」と不安を抱える人もいるでしょう。 高校生が学校に行きたくないと思う背景には、学業の悩みや人間関係の不安などさまざまな理由があります。子どもの意思を尊重して慎重に解決策を見つけることが大切です。
-
 起立性調節障害の子どもに親ができること|改善には接し方や理解が大切
起立性調節障害の子どもに親ができること|改善には接し方や理解が大切
「起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)」をご存知でしょうか。起立性調節障害は、病院で診断、治療を受けることができる病気のことで、朝起きられないなど起床時に症状が強く出て、登校が難しくなりがちになることが特徴です。小学生や中学生などで不登校になっている子どもの3~4割が、起立性調節障害であるともいわれています。本記事では、起立性調節障害の主な症状、原因、診断の流れ、親ができること、改善のためのポイントなどについて解説します。
-
 不登校に関する悩みの相談先を紹介!不登校の学生が抱えやすい悩みも解説
不登校に関する悩みの相談先を紹介!不登校の学生が抱えやすい悩みも解説
不登校になる原因はいじめや勉強不振、人間関係などさまざまです。このような悩みを親に打ち明けるのは勇気がいることであり、まずはほかの相談先を探しているという場合も多いでしょう。 本記事では、学校など対面での相談先だけでなく、電話やメールで相談できる相談先も紹介します。
-
 不登校の支援先や団体、施設を紹介!支援を受けるメリットも解説
不登校の支援先や団体、施設を紹介!支援を受けるメリットも解説
不登校への支援は単に「再び登校できるようになるためのサポート」だけではありません。子供が進路を主体的に考え、社会的な自立を目指せるように支援することが基本的な目的です。 そこで本記事では、不登校の子供が利用できる公的な支援機関や相談機関、民間団体、民間施設を詳しく紹介します。
-
 HSCが不登校の原因になる?親が取るべき対処法をご紹介
HSCが不登校の原因になる?親が取るべき対処法をご紹介
HSCの子供は刺激に対して敏感で、学校で過度にストレスを感じることがあります。ストレスが極限まで溜まると、急に学校に行かなくなる子も少なくありません。そこで今回は、HSCの子供が不登校になる原因や親が取るべき対処法をご紹介します。
-
 中学生が不登校になる原因は?親の対応方法やNG行動を徹底解説
中学生が不登校になる原因は?親の対応方法やNG行動を徹底解説
中学生になると男女ともに思春期に入り、小学生の頃よりも人間関係が複雑化します。また勉強の難易度が高くなるため、授業についていけなくなる子もいるでしょう。このような中で、不登校になる中学生もいます。自分の子どもが不登校なると、親としてはとても不安になるでしょう。この記事では、不登校の現状や中学生が不登校になる原因、親の対応方法について解説します。
-
 不登校は甘えてるだけ?甘え依存型(混合型)不登校の特徴と注意点
不登校は甘えてるだけ?甘え依存型(混合型)不登校の特徴と注意点
「学校に行かないのは甘えだ」「親の顔色をうかがってわがままになっている」そんな声を耳にしたことがあるかもしれません。不登校の子どもを持つ保護者は、「本当にこれでいいのか」と悩み、葛藤することもあるでしょう。 この記事では、「甘え依存型(混合型)」と呼ばれる不登校のタイプについて解説していきます。
-
 不登校でひきこもりの子どもは外出させるべき?親が注意すべき点や相談先
不登校でひきこもりの子どもは外出させるべき?親が注意すべき点や相談先
不登校やひきこもりの問題は、子どもを育てる親にとって大きな悩みとなっています。この問題にどう対応すれば良いのでしょうか。 この記事では、不登校やひきこもりの子どもを持つ親に向けて、具体的な対応方法や注意点、相談先について詳しく解説します。
-
 不登校の中学生には何をさせる?時期別の過ごし方や家以外の選択肢
不登校の中学生には何をさせる?時期別の過ごし方や家以外の選択肢
中学生の子どもが不登校になったとき、「家で何をさせる?」「自宅以外で何をしている?」と気になる人もいるのではないでしょうか。 文部科学省の調査によると、「インターネット・ゲーム・動画視聴など」が8割以上にのぼりました。 この記事では、不登校中の中学生の適切な家での過ごし方や、自宅以外の選択肢について紹介します。
-
 不登校でもテストを受けた方がいい?高校受験との関係と受ける方法
不登校でもテストを受けた方がいい?高校受験との関係と受ける方法
中学生の不登校で、保護者が抱く大きな不安の要素のひとつが「高校進学をどうするか」です。成績をつけてもらうには授業はともかくテストぐらいは受けた方がいいのでは、と感じる保護者も多いでしょう。 この記事では、不登校の中学生とテストの関係、テストを受ける方法や注意すべきポイントについて解説します。
-
 別室登校で不登校を解決できる?保健室登校との違いも解説
別室登校で不登校を解決できる?保健室登校との違いも解説
別室登校とは、教室で授業を受けられない生徒が、自分のクラスの教室とは別の場所で学校生活を送る方法です。 不登校が増加する中、心理的な負担を軽減しながら学校との繋がりを保つ方法として注目されています。 この記事では、別室登校のメリット・デメリットについて整理します。また、保健室登校との違いについても解説します。
-
 不登校のあるある行動には理由がある?子供に合わせた対処法とは
不登校のあるある行動には理由がある?子供に合わせた対処法とは
年々不登校となる子供の数は増える一方ですが、それぞれの状況や程度はまったく異なります。取り巻く家庭や学校の環境まで違うのに、起きることや行動には似たところがあるのは不思議です。 この記事では、不登校の子供によくみられる行動や起きること、いわゆる「あるある」について解説します。
-
 不登校の親は仕事をやめるべき?続ける方法も解説
不登校の親は仕事をやめるべき?続ける方法も解説
子供が不登校になった時、仕事を続けるべきか、辞めるべきかについて悩む親もいるでしょう。この記事では、仕事を続けるメリット・デメリットのほか、不登校の子供への対応と仕事をどうすれば両立できるのかについて、具体的な解決策を提示します。
-
 不登校をしたら後悔する?しない?子供の後悔と親の後悔を解説
不登校をしたら後悔する?しない?子供の後悔と親の後悔を解説
不登校状態にある子供が身近にいる場合、将来、不登校をしていたことで何らかの後悔するのではないかと心配したり不安に感じたりしている人もいることでしょう。 この記事では、子供が不登校で学校に行けなかった場合、将来、学校を卒業してから後悔するようなことが起こり得るのか、子供が不登校状態にあることを自分のせいだと後悔している親はどう気持ちを切り替えればよいのかなどを解説します。
-
 不登校の期間は人それぞれ!回復のステップや見極めのポイントを紹介
不登校の期間は人それぞれ!回復のステップや見極めのポイントを紹介
不登校は短い期間で終わる人もいれば、回復までに長い時間がかかる人もいます。自分の子供が不登校になったとき、いつまでこの状況が続くのかと悩む親も多いでしょう。 回復に向けたステップとそれぞれの特徴を知ることで、不登校からの回復に関する理解が深まります。今回は、不登校からの回復に要する時間や回復過程などをみていきましょう。
-
 不登校はわがままではない!わがままと感じるシーンや適切な対応を解説
不登校はわがままではない!わがままと感じるシーンや適切な対応を解説
子供が不登校になると、学校に行かないのはわがままだと感じる親もいるかもしれません。しかし、子供は不登校によってわがままになるわけではありません。不登校は、子供が自分自身を守るための手段なのです。 わがままに見える行動の理由を知ることで、親として適切な対応ができるようになります。今回はわがままだと捉えられるシーンを紹介し、不登校の子供に必要な対応を解説します。
-
 不登校で昼夜逆転してしまう5つの原因と親がいまできること
不登校で昼夜逆転してしまう5つの原因と親がいまできること
不登校の子どもを持つ保護者の多くが、子どもの「昼夜逆転」の悩みに直面しています。夜眠れず、朝起きられない…。そんな日々が続くと、「このままで大丈夫なのだろうか」と不安を感じるのは当然です。 この記事では、不登校と昼夜逆転の関係、主な原因、親としてできる具体的な対応策をまとめました。
-
 不登校が再発したら?不登校の再発防止と再発した場合の対処について
不登校が再発したら?不登校の再発防止と再発した場合の対処について
不登校の再発は、比較的よく起こることです。不登校を克服して学校に通えるようになったあとで、不登校が再発してまた通えなくなることは決して珍しいことではありません。 しかし、家族や周囲の大人たちにとっては「せっかく学校に通えるようになったのに」や「不登校の状態に逆戻りしてしまった」など、不登校が再発したことに対して、不登校になったとき以上に焦りや戸惑いを強く感じることが多いことでしょう。 子供の不登校が再発した場合、周囲が落胆したり焦ったりするのではなく、なぜ再発したのかを見極めて対処することが大切です。本記事では、不登校再発の原因や再発防止のためにできること、再発した場合の対処法などについて説明します。
-
 不登校の居場所づくり|子どもが安心できる環境は?
不登校の居場所づくり|子どもが安心できる環境は?
不登校の子どもにとって、家庭以外でも自分を受け入れてくれる場所があるかどうかは重要な問題です。中には家庭でさえも落ち着ける環境ではなく、居場所がないと感じている子どももいます。不登校の居場所としては、教育支援センターやフリースクールなどさまざまな選択肢があります。専門的な支援を受けられる機関やコミュニティとのつながりを持つことで、家族全体の精神的負担も軽減されます。不登校の解決には時間がかかることが多いですが、安心できる居場所があることで、子どものストレスが軽減され、社会復帰の準備が進むでしょう。
-
 不登校からの留学は可能?メリットや注意点を正しく理解しよう!
不登校からの留学は可能?メリットや注意点を正しく理解しよう!
一口に不登校といっても「本当は学校に行きたいけど行けない」「これといって理由はないけど行きたくない」などさまざまな形があります。何らかの理由で不登校になってしまった時に、その解決方法の1つとしてあるのが「海外留学」です。 「日本の学校は自分に合わない」「海外で環境を変えてみたい」と不登校から海外留学を決断する人は多くいます。しかし、「自分は海外でうまく適応できるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。 そこで、本記事では不登校から海外留学するパターンや得られるメリット、注意点などを解説します。
-
 子どもが不登校の親の悩み。不登校になりやすい親の特徴とは?
子どもが不登校の親の悩み。不登校になりやすい親の特徴とは?
子どもが不登校になり、不安や悩みを抱えている保護者の方もいるでしょう。 「不登校の子を抱える他の保護者はどうしているのか」「どんな悩みを抱えているのか」など気になる人もいるのではないでしょうか。 この記事では、アンケート調査を元に、不登校の親の実態を紹介し、子どもが不登校になった場合の相談窓口を紹介します。
-
 不登校の中学生の進路は?進学しやすい高校や進路を選ぶ際の注意点
不登校の中学生の進路は?進学しやすい高校や進路を選ぶ際の注意点
不登校の中学生を持つ親にとって、子どもの進路についての悩みは切実です。「中学を卒業できるのか」「高校に行けるのか」という不安を抱えている人もいるでしょう。中学で不登校でも、高校に行くことは可能です。この記事では、不登校の中学生でも進学しやすい高校や、進路を選ぶ際の注意点について解説します。
-
 不登校への対応はどうする?まずやるべきこと5つとNG行動
不登校への対応はどうする?まずやるべきこと5つとNG行動
不登校の子どもは年々増加しています。子どもが不登校になった際、保護者はどのように対応すべきでしょうか。 この記事では、不登校の子どもへの具体的な対応5つと避けるべき行動について解説します。
-
 高校で不登校だと進路はどうなる?中卒だと将来不利?
高校で不登校だと進路はどうなる?中卒だと将来不利?
中学校で不登校のために、高校へ進学しなかったり、中退したりしてしまうと、最終学歴は中卒です。高校は義務教育ではありませんが、中卒と高卒とでは、進学や就職で選べる進路の幅が異なります。 この記事では、中卒と高卒の違いや、不登校でも高卒資格を取得する方法について紹介します。
-
 不登校でも就職できる?不利になる理由や成功率を上げる方法
不登校でも就職できる?不利になる理由や成功率を上げる方法
中学や高校で不登校の経験があると、「就職できないのでは?」「就職に不利になるのでは?」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか。 不登校の経験があるからと言って、就職できないということはありません。 不登校の理由や何をしていたかなどを、きちんと説明できるようにしておけば問題ありません。 この記事では、不登校だと就職が不利になる理由や、不登校経験者が就職活動を成功させるポイントなどについて解説します。
-
 高校で不登校でも大学受験はできる?大学に行きたいなら抑えておくべきポイント
高校で不登校でも大学受験はできる?大学に行きたいなら抑えておくべきポイント
高校で不登校の経験があると、「大学受験は難しいのでは?」と感じるかもしれません。 でも安心してください!不登校の経験があっても、大学進学は可能です。 この記事では、高卒認定や通信制高校など、あなたが夢を実現するための具体的な方法や勉強法を紹介します。
-
 不登校の自宅学習どうする?勉強遅れを取り戻す方法
不登校の自宅学習どうする?勉強遅れを取り戻す方法
不登校の中学生を持つ親にとって、自宅学習をどのように進めるかは悩みのひとつです。「勉強が遅れないか」「遅れが取り戻せなくなるのでは」と不安になることもあるでしょう。しかし、学習環境を整え、計画的に学習をしていれば、勉強が遅れてしまうということはありません。この記事では、家庭学習をする際の準備や、具体的な自宅学習の方法について解説します。
-
 高校に行きたくない中学生に知っておいてほしいこと
高校に行きたくない中学生に知っておいてほしいこと
中学生の皆さんの中には、「高校に行きたくない」という気持ちを持っている人もいるでしょう。 人間関係や勉強への不安から、高校に行きたくないと思うことは、決して珍しいことではありません。 「高校に行く」以外の道を選ぶこともできますが、「高校に行かないとどうなるか?」について理解しておくことは重要です。 この記事では、高校に行きたくないと感じている中学生に向けて、選択肢や解決方法、将来のビジョンについてアドバイスします。
通信制高校ガイド 人気ランキング
-
【保存版】通信制高校の学費は?無償化・支援制度で負担を抑える方法

通信制高校の学費を徹底解説。就学支援金などの公的制度で授業料が実質無償化されるケースもあります。この記事では、支給対象や支給額の目安、申請時の注意点などをわかりやすく解説します。費用負担を抑えられるのでチェックしてみましょう。
-
通信制高校から大学進学は不利?おすすめの通信制高校5選も紹介

通信制高校への入学を検討していて「大学進学に不利になるのではないか」「通信制高校から行ける大学はある?」と不安に思うご家庭もあるのではないでしょうか。 結論として、通信制高校に通っているからといって大学進学に不利になることはありません。中には、大学進学を想定したカリキュラムを用意しているケースも増えており、難関大学の合格実績を豊富にもつ学校もあります。
-
サポート校とは?通信制高校との違いや利用の判断基準

サポート校とは、通信制高校に通う生徒を学業面や生活面でサポートする教育機関です。通信制高校へ通う生徒が、学校と合わせて利用するため、サポート校のみでは高卒資格を取得できません。 ただし、個別の学習指導やスクールカウンセラーによる生活面での相談など手厚い支援が受けられるため、生徒がより楽しく高校生活をおくるための助けとなるでしょう。 この記事では、サポート校の特徴や通信制高校との違い、メリット・デメリットについて解説します。
-
通信制高校に行ったら人生終わり?終わりではない理由やメリットを解説

通信制高校を検討している人の中には、「通信制高校に行ったら終わり」「通信制高校はやめとけ」というネガティブな情報を目にしたことがある人もいるのではないでしょうか。 結論から言うと、通信制高校に行ったからといって「人生終了」では決してありません。通信制高校では自分のペースで学べる、専門的なコースで好きなことを学べるといった、多くのメリットがあります。 この記事では、通信制高校に行くことが人生終わりではない理由や、通うメリット・デメリット、目標に合わせた高校選びについて解説します。
-
通信制高校に通う普通の子はいる?生徒の特徴や向いていない人の特徴まで解説

「全日制の高校に通うことが普通」という思い込みから、通信制高校への入学に不安や疑問をもつ人もいるのではないでしょうか。 通信制高校は「不登校の生徒」や「持病のある生徒」などが通う学校という、先入観がある人もいるかもしれません。 実際には、通信制高校への入学者は増加傾向にあり、さまざまな生徒が在籍しています。 この記事では、通信制高校にはどのような生徒が通っているかや、通信制高校に向いていない生徒の特徴などについて解説します。
入学してやりたいこと、送りたい学校生活などを思い浮かべて検索!夢を叶えられる学校が簡単に見つかります。
学校を探す