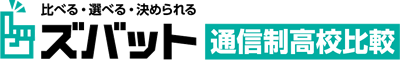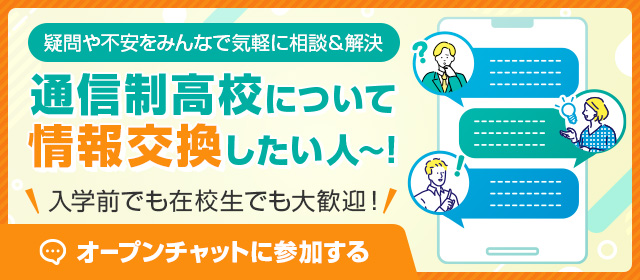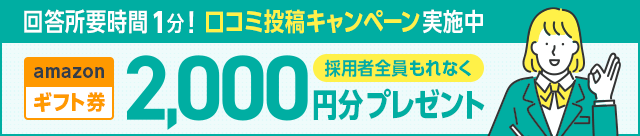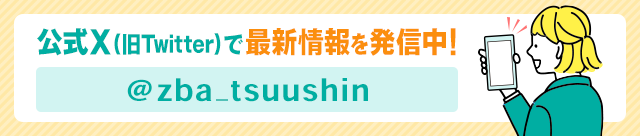不登校で昼夜逆転する原因とは?改善のために保護者ができること
公開日:2021年08月12日 更新日:2021年08月12日

大人が昼夜逆転した生活を送っていると、「だらしない」「不健康」などといわれることも多いでしょう。そのため不登校の子供の生活が昼夜逆転すると保護者は、子供が将来仕事をきちんとできるようになるのか、不登校が悪化しないかが心配で、なんとしてでも改善しないといけないと考えます。 昼夜逆転を改善するには原因を正しく把握し、保護者も細心の注意を払って子供に接し、できることをしっかり行うことが必要です。 ここでは、不登校で生活が昼夜逆転してしまう仕組みと、保護者や本人が改善のためにできることを解説します。
不登校で起きる昼夜逆転とは
学校に行っていれば朝起きて登校し、好き嫌いはあるにせよ勉強や運動などしっかり活動して帰宅するというリズムに沿った毎日を過ごします。
それが不登校になると良くも悪くも活動の「きっかけ」がなくなり生活リズムが乱れ始め、長期にわたると生活全体が昼夜逆転することもめずらしくありません。
不登校の子供が昼夜逆転する主な原因は「眠れない」こと。しかしこれにもいくつかのパターンに分かれ、原因や理由の種類や程度も一人ひとり違います。夜遅くまで動画を見たりゲームをしたりしていたとしても、そうせざるを得ない理由があるのかもしれません。単に動画を見たり、ゲームをしたりするのを止めれば夜眠れるとは限らないのです。
不登校の昼夜逆転を解消するには、まずその原因を知る必要があります。
不登校の子供が昼夜逆転する4つの原因
子供としても、きっと昼夜逆転したくてしているわけではありません。不登校の影響で生活リズムが乱れ、結果として昼夜逆転しているとすれば、そのメカニズムを知ることで対処できるはずです。ここでは不登校の昼夜逆転の代表的な4つの原因を解説します。
1.生活環境の変化によるストレス
大人でも深刻な悩みがあれば夜眠れなくなることはあります。それがまだ幼い子供なら眠れないのも仕方ないでしょう。例えば、小学校から中学校、中学校から高校への進級、保護者の仕事の都合などによる転校は、子供の世界の大半を占める「学校」という環境が丸ごと変わる大きな変化です。友達や先生とどう付き合うかなど抱えるストレスは多くなります。
それ以外にも成績不振や将来への不安など悩みは尽きません。このようなストレスは不登校だと学校に行っていない分、より深刻な悩みに発展することもあります。食事も不規則になり、ますます生活リズムが乱れても不思議ではありません。
2.学校という生活習慣や時間の基準がない
学校に行くなら朝の登校、食事としての給食、昼休みや授業などすべて定められた「時間」に沿って行動することが求められますが、不登校ではこれらすべてが自己管理です。
これは大人が仕事の休みの日に、いつも通り早起きして規則正しく過ごすことを思えば、どれほど難しいかわかります。子供が昼夜逆転するまでリズムが乱れるのは仕方ないかもしれません。
3.スマホやゲームへの依存
時間を縛る基準がないということは、自分が好きなことをいつまでもやれるということでもあります。「好きなこと」とは例えばテレビ番組や音楽、読書といったものがありますが、最近ではスマートフォンやスマートフォンでプレイできるゲームもその1つです。不登校でやり場のないエネルギーを発散するには、最も身近で手軽な方法だといえます。
特にスマホゲームは、製作者が「いつまでもプレイしてもらえる」よう設計していることもあり、子供が非常に熱中しやすいものです。またほかのプレイヤーと協力して進めるタイプのゲームの場合、プレイ時間が社会人プレイヤーが参加しやすい深夜に集中しがちという特徴があります。その結果、昼夜が逆転してしまうのです。
4.心や体の病気の可能性も
不登校や昼夜逆転は、子供本人だけではどうしようもない心や体の「病気」が関係していることもあります。病気や障害が原因で不登校になるパターンや、逆に不登校や昼夜逆転が元で病気になるパターンがあり、特に心の病気の場合は本人にも自覚がなく、保護者もまったく気づかなかったということもめずらしくありません。
例えば、徐々に就寝時間が遅くなることから起床時間も遅くなってしまう「睡眠相後退症候群」や、自律神経系の異常により循環器系の調節がうまくいかなくなる「起立性調節障害」、気分が強く落ち込み眠れない、疲れやすいといった身体的な症状が現れることもある「うつ病」はその一例です。このような場合は速やかに医療機関を受診するなど専門家に相談しましょう。
昼夜逆転の改善で保護者ができること
昼夜逆転にはさまざまな原因がありますが、特に学校関連でストレスを溜めている場合は、家庭は貴重な「安心できる場所」になるはずです。こんなとき子供にとって保護者のサポートは改善に役立つ役割を果たします。
昼夜逆転を受け入れ子供の話を傾聴する
子供が安心していられるには、例えば帰ってきたら「おかえり」と笑顔で出迎えてくれたり、自分の好きなことの話を聞いてくれたりといった、周囲の人の理解と対応が大切です。顔を見るごとに「朝8時までに起きなさい」とか「勉強しているの?」などといわれればストレスがたまり、昼夜逆転の改善は難しくなります。
保護者はまず、昼夜逆転している現実を受け入れ、無理に起こしたりせず子供が話してきたらいつでも傾聴できるよう備えましょう。
子供の味方として徹底したサポートにまわる
不登校や昼夜逆転について、一番悩んでいるのは人生がかかっている子供本人です。しかし子供は知識や経験が乏しいのでどうすればいいかわかりません。そんなときこそ保護者の出番です。昼夜逆転を改善するため「明日は少しがんばって朝10時までに起きてみない?」などできそうな目標を示し、子供の抱える悩みを共有して「あなたの味方だよ」というメッセージを目に見える態度や行動で示しましょう。
提案した際に難しそうな顔をしていたら、もっとできそうな目標に変えても構いません。保護者は子供ができることを徹底的にサポートする側にまわりましょう。
先生や友達など周囲の力を借りることも
不登校の子供の保護者は、どこか「自分がなんとかしなくては」と強く思い込みがちです。しかし大切なのはあくまで子供の不安の解消であり、保護者だけで解決することではありません。必要に応じて先生や友達、カウンセラーなどの力を借りることを柔軟に検討するのは保護者の重要な役割だといえます。
『自分に合う通信制高校がわからない』『おすすめの学校を提案してほしい!』
そんな声にお応えして、【通信制高校診断】をご用意しました。60秒で診断完了できます!
子供自身でできる昼夜逆転の改善への取り組み
一方で、昼夜逆転を子供自身で改善する方法もあります。子供が「どうすればいいかわからない」状態であれば、保護者も一緒に次のようなことを意識すると改善できる可能性があります。
生活のリズムを整える
昼夜逆転の原因の1つは「時間的な縛りがない」ことです。もっとも注目されがちなのは「朝起きる時間」ですが、生活のリズムはほかに食事や就寝時間も大きく影響します。例えば「寝る時間」や「食事の時間」を決め、時間を意識する習慣をつけることから始めるのも良いでしょう。
時間を意識する習慣がつけば、好きなことをしていても「あと◯時間したら寝よう」「もうすぐ食事だ」と自分で区切りをつけられるようになってきます。生活リズムを整えるにはまず、時間を意識することから始めましょう。
日中に体や頭を使う
うまく入眠するためには適度なエネルギー消費も必要です。例えば寝る前に読書をしたり、クイズやパズルを解いたり、頭を使うことがおすすめです。また夕方から夜までの間に20〜30分ほど近所を散歩したり、庭でトレーニングしたりと体を動かすこともスムーズな入眠を促します。
ほかにも、体温を適温に調節する時間が必要なため、入浴は寝る2時間前までに済ませる、寝る前はブルーライトの刺激が睡眠の妨げになるのでパソコンやスマホを使わないことも大切です。
昼夜逆転の改善は徹底したサポートから
不登校の子供の昼夜逆転には原因がありますが、子供が意図して昼夜逆転していることはおそらくないでしょう。保護者ができるのは昼夜逆転の原因をともに考え、改善のためにできる目標を示して一緒に解決しようと努めることです。
保護者はまず昼夜逆転している事実をしっかり受け止め、これからどうするかを子供と一緒に考える必要があります。時には先生や友達など周囲の力を借りることも検討するべきでしょう。
大切なのは保護者が、徹底して子供の味方であることを示し、サポートすることです。子供の昼夜逆転を改善し、毎日が暮らしやすくなるよう関係者が全員で取り組むよう努めましょう。
『自分に合う通信制高校がわからない』『おすすめの学校を提案してほしい!』
そんな声にお応えして、【通信制高校診断】をご用意しました。60秒で診断完了できます!