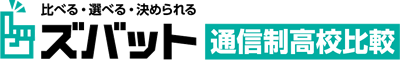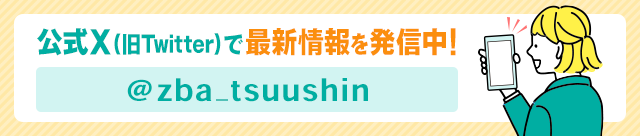別室登校で不登校を解決できる?保健室登校との違いも解説
公開日:2021年09月09日 更新日:2025年03月18日
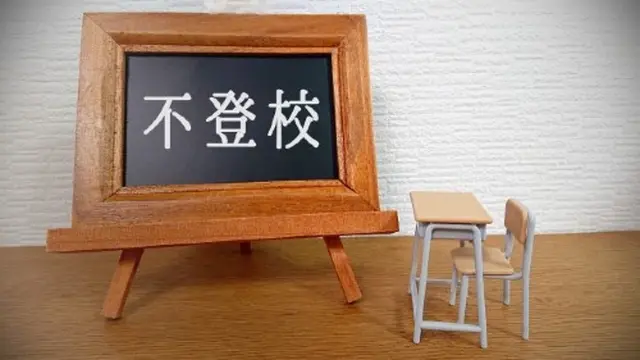
別室登校とは、教室で授業を受けられない生徒が、自分のクラスの教室とは別の場所で学校生活を送る方法です。 不登校が増加する中、心理的な負担を軽減しながら学校との繋がりを保つ方法として注目されています。 この記事では、別室登校のメリット・デメリットについて整理します。また、保健室登校との違いについても解説します。
別室登校とは?
自分のクラスの教室に行かず別の部屋で過ごすことをいいます。図書館や進路指導室、カウンセリングルームなどが利用される場合が多いです。
不登校の子どもが学校に戻る際、いきなりクラスの教室に入るのはハードルが高いです。そのハードルを下げるためにも、教室以外の別室に一時的な避難所として居場所を作り、教室に戻るためのステップとして利用します。
一般的に、別室登校は学校に登校して学習活動を行うため、中学校では出席扱いとなります。これは保護者と子どもにとって大きな安心材料といえるでしょう。
なお、一部の授業をクラスの教室で受け、大半は別の部屋にいる場合も別室登校に含まれます。
別室登校での過ごし方
別室登校では勉強や読書、先生と会話などをして過ごします。別室登校をしたらこれをやらないといけないという決まりはなく、ストレスの少ない環境で学習を続けられます。
自習をする子もいれば、会話だけをして帰る子もいるでしょう。帰宅時間も自分に合ったタイミングで決められるため、生活リズムも調整しやすいです。
先生の都合が合えば、クラスで行われている授業の内容を教えてもらうことも可能です。ただし、いつも先生がいてくれるとは限らないため、基本的には勉強は自分で進める必要があります。
保健室登校・放課後登校との違い
別室登校と似た言葉として、「保健室登校」「放課後登校」があります。
保健室登校は、体調不良や精神的な疲れがある場合に、一時的に教室を離れ、保健室で休息することをいいます。学習よりも休息に重点が置かれるため、勉強面でのサポートは限定的です。
放課後登校は、学校の通常授業が終了した後に登校し、個別に指導を受ける形式です。通常の授業時間に教室に行くのが難しい生徒にはありがたいものの、放課後に時間を割く必要があるため、通常とは異なる生活リズムを維持する必要があります。
また学校によっては、相談室に登校し支援員と過ごす方法もあります(相談室登校)。相談室は、生徒がよりリラックスして過ごせる空間で、心理的なサポートも充実しています。支援員は専門的な訓練を受けており、生徒のニーズに合わせたサポートが期待できます。
別室登校をするメリット
別室登校には、以下のメリットがあります。
- 出席扱いとなる
- 子どもの孤立を防げる
- 生活リズムの乱れを防げる
- 学校との繋がりを持てる
- 教室復帰のきっかけを得やすい
出席扱いとなる
別室登校は多くの中学校で出席扱いとなります。これは、「クラスの教室にいなくても、学校に来ていれば欠席者ではない」という考えに基づくものです。
出席の状況は内申点にも関わるため、進路選択に大きな影響を与えかねません。高校受験の際には、高校によって内申点を重視する場合もあり、別室登校による出席扱いは不登校の子どもにとって大きな意味を持ちます。
子どもの孤立を防げる
別室登校は、子どもの孤立を防ぐために効果的です。通常の教室に入るのが難しい状況でも、学校内の別の部屋で学ぶことで、ほかの生徒とも交流を持つことができます。
人との繋がりに慣れ、お互いを理解しあって交流できれば、教室復帰した際の孤立を防げます。別室登校が人との信頼関係を作るきっかけにもなるでしょう。
生活リズムの乱れを防げる
「不登校中に家庭で昼夜逆転していた」「なかなか早起きができない」など、生活リズムが乱れてしまう生徒もいます。別室登校は生活リズムの乱れをリセットし、学校生活に沿ったリズムに合わせるきっかけとなるものです。
別室登校でも、学校にいることで「チャイムが鳴ったら授業が終わる」「学校に遅刻しないために、この時間に家を出る」といった意識付けになります。
また、学校のタイムスケジュールにあわせて行動することで、規則正しい生活を送ることができるようになります。別室登校は生徒が心身ともに健康を保ち、不登校の原因であるストレスや不安を軽減する効果も期待できます。
親と学校が繋がりを持てる
別室登校で学校に行けるようになれば、親と学校が繋がりを持てるというメリットもあります。
不登校の間は学校との接点がなくなり、連携が難しいと感じる場合があるでしょう。しかし短時間でも子どもが学校に行けるようになると、学校での子どもの様子を先生から聞いたり、今後のことを相談したりできます。
また、学校側も親から情報を得ることで、より適切な指導やサポートを提供できるようになります。親と学校が一体となって子どものために動くことで、子どもの学校生活の改善を目指せます。
教室復帰のきっかけを得やすい
不登校から別室登校に移行すれば、教室復帰のきっかけを得やすくなるのがメリットです。学校内の別の部屋で学習することで、徐々に学校という環境に再び慣れることができます。
学校にいれば、先生やクラスメイトとコミュニケーションをとる機会も出てきます。それらを通じて、「そろそろ教室に行こうかな」と教室復帰に対して意欲的になることもあるでしょう。
別室登校で少しずつクラスメイトと交流しながら、子ども自身がきっかけを得るのを気長に待ってあげましょう。
別室登校をするデメリット
別室登校には、以下のデメリットがあります。
- 学習が遅れる
- 罪悪感におそわれる
- 別室登校で満足してしまう
- 人の目が気になる
学習が遅れる
クラスの授業に出られないことで生じる学習面の遅れは、別室登校のデメリットとして挙げられます。学習の遅れは生徒の自信を喪失させ、不安を増大させる要因にもなります。
家庭内で勉強のサポートを受けながらある程度の学習は進められますが、すべての内容をカバーするのは難しいでしょう。
また別室登校では一人で自習する時間が長くなります。自分の力だけで学校の授業内容に追いつけるかどうかは人それぞれです。
罪悪感におそわれる
ほかのクラスメイトとは異なる別室登校という状況に、子どもが罪悪感を持ってしまう可能性もあります。
学校に行くと、自分のクラスメイトが教室で授業を受けているのを目の当たりにします。それに対して、「自分は別室にいるだけで、周りからさぼっていると思われるのではないか」などと後ろめたい気持ちになることがあります。
子どもだけでなく、保護者も後ろめたさを感じやすいです。子どもが不登校になってしまった原因について、自らを責めることもあるでしょう。
人の目が気になる
別室登校では、学校の先生やクラスメイトとのコミュニケーションがとれる一方で、人の目が気になるというデメリットもあります。
別室登校を特別扱いだとして、周りの人から「ずるい」と言われる可能性も考えられます。特に子ども同士の言葉は辛辣で、「なんであの子は午前中で帰っていいの?」「授業出ないで帰るの羨ましい」などといった心ない言葉に傷つき、つらい思いをするケースもあるでしょう。
まだ不安定な状況の子どもにとって、これらの言葉が不登校へ逆戻りするきっかけになってしまう場合があります。
別室登校で満足してしまう
別室登校により、学校に通うことができるようになると、「学校には行けているからこれで大丈夫」と自分に満足してしまうケースがあります。
不登校からの第一歩を踏み出せたと評価できる一方、別室登校が心地よくなり、その環境に慣れてしまうことも考えられます。
別室登校によって子どもが現状に満足してしまうと、教室復帰という次のステップに進めなくなるケースもあります。教室復帰を目指すのであれば要注意です。
別室登校の次のステップとは?
別室登校から教室復帰を目指すには、段階を経ていくことが大切です。始めから教室で1日過ごすのではなく、得意な教科の授業だけ参加したり、教室で給食を食べてみたりするのがよいでしょう。
子どもの状況に合わせて、焦らずに少しずつ教室復帰を目指します。別室登校から教室復帰までの具体的なステップは、以下の通りです。
1.友達に別室に来てもらう
はじめのうちは、仲の良いクラスメイトに別室に遊びに来てもらいます。
一緒に過ごしているうちに、孤立感が減り、学校全体との繋がりを感じやすくなります。友達との交流が増えることで、クラスに戻りたいという意欲がわいてくるかもしれません。
2.決めた時間のみ教室に戻る
別室登校で自信がついたら、クラスの教室に戻る時間を設けます。得意な教科の時間や給食の時間であれば、戻りやすいことがあります。
ただしクラスメイトのなかには「なんでこの時間だけ来るんだ」と言ってくる人もいるかもしれません。先生とよく話し合うなどして、周囲に理解を得られるように取り組む必要があるでしょう。
3.少しずつ教室に行く回数を増やす
授業に少しずつ参加できるようになったら「2時間目まで」といったように、教室に行く時間を決めるのもよいでしょう。目標を決める際は子どもだけでなく、親や養護教諭、担任で協議します。
子どもにとって無理のない範囲で、教室で過ごす時間を徐々に増やしていきましょう。
4.教室復帰
すべての時間を教室で過ごせるようになれば、教室復帰です。
これらのステップは、あくまでも一例です。焦って教室に戻そうとしたり、無理矢理クラスメイトと顔を合わせようとしたりするのは逆効果になりかねません。教室復帰に向け、慎重にステップを歩むことが復帰への近道といえるでしょう。
まとめ
別室登校は、学校に行くことが難しい生徒にとって有効な選択肢のひとつです。精神的な負担を軽減しながら学校とのつながりを保ち、学習の遅れを最小限に抑えることができます。
別室登校から徐々にステップを踏んでいくことで、やがて教室復帰できるチャンスも出てくるでしょう。
とはいえ、不登校から学校復帰するだけが不登校の解決ではありません。自分で勉強して進学する方法もありますし、やりたい仕事を見つけて手に職をつけるための道に進むのも解決策の1つといえます。
子どもの状況や将来を考え、さまざまな選択肢を用意することも親の役割です。不登校からの進路については、『不登校の中学生の進路は?進学しやすい高校や進路を選ぶ際の注意点』も参考にしてください。