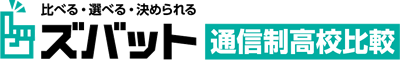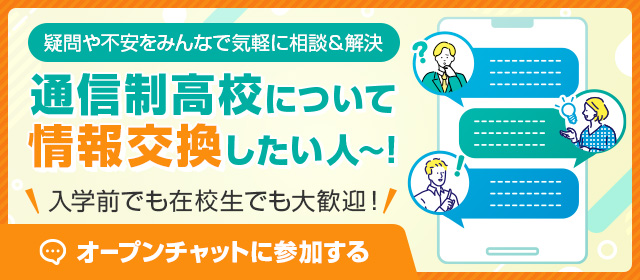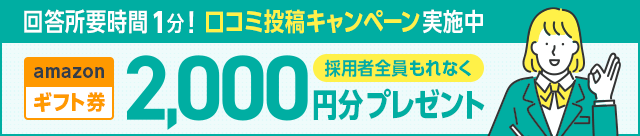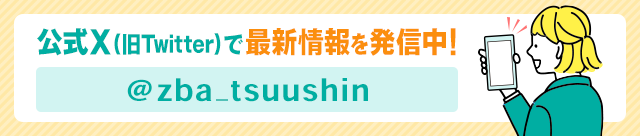【学校での「ぼっち」対処法】ひとりぼっちの原因、対処法や心の持ち方を知ろう
公開日:2021年09月13日 更新日:2024年02月26日

学校で周りのクラスメイトと馴染めず、教室にひとりでいる時間が長くなると、「ひとりぼっち(ぼっち)」の状況に陥ります。ひとりぼっちでいることが必ずしも悪いわけではありませんが、もし解決したいと考えているなら、まずは原因を探り、対処法や自分の心の持ち方を知ることが大切です。
- 学校でひとりぼっちになる4つの原因
- ひとりぼっちを解決するには?あえて逆手に取る方法もアリ
- 学校以外で自分の居場所を見つける方法
- つらいひとりぼっちに対処する3つの考え方
- 学校でのひとりぼっちを相談できる窓口
- ひとりぼっちは悪いことではないけれど、状況を変えるのは自分次第
学校でひとりぼっちになる4つの原因
ひとりぼっちとは、友人や仲間がおらず孤独である様子を指します。学校でひとりぼっちでいる状態を「寂しい」と感じる人もいれば、ひとりぼっちを「気楽で良い」と感じる人もいますが、ひとりぼっちでいる自分を「このままではいけない」と不安に感じることもあるでしょう。
学校でひとりぼっちになる原因としては、「コミュニケーションを避けている」「何らかの劣等感がある」「自己中心的な考えである」「ネガティブな思考」の4つが挙げられます。自分では気付きにくいこともあるため、どのような原因があるかを正しく理解しておくとよいでしょう。
1. 他人とのコミュニケーションを避けている
1つ目の要因は「他人とのコミュニケーションを避けている」です。学校でひとりぼっちになりやすい人は、自分からコミュニケーションを取るのが苦手で、話すきっかけを作るのが難しいと感じています。コミュニケーションが苦手だと感じている人は、以下のような考えを持っている場合が多いです。
- ・クラスの雰囲気は好きだけど、何を話せばよいかわからない
- ・みんなが話している内容が気になるけど、輪の中に入っていけるか不安
- ・仲良くなれそうな人がいたけど、どう話すきっかけを作ればよいかわからずにいる
このように、自分からのコミュニケーションへの苦手さを持っている人がほとんどですが、相手から話しかけられれば友達を作れる可能性があります。小さなきっかけから勇気を出して、コミュニケーションを取るとよいでしょう。
2. 何らかの劣等感を持っている
2つ目の要因は「何らかの劣等感を持っている」です。自分に自信がなく、他者と比べてしまうタイプを言います。劣等感を持っている人は、以下のような考え方を持っている場合が多いでしょう。
- ・他者に受け入れてもらう自信がない
- ・話しかけてもつまらないと思われるだろう
- ・あの人と友達になりたいけど、自分なんかとは釣り合わないと思っている
このように、自分にまったく自信がないと人間関係を作るきっかけを作れず、いい人間関係を築くのが難しくなります。また、ひとりぼっちになるとさらにネガティブな思考に捉われるようになり、「自分のことなんて、誰も相手をしてくれない」と思ってしまうことがあるのです。
まずは自分の良いところを見つけ、自己肯定感を高めると良いでしょう。自分ががんばったことやほめられるポイントなどを書き出すと、自分の良い点を見つけられるようになります。
3. 考え方が自己中心的である
3つ目の要因は「考え方が自己中心的である」です。コミュニケーションを取るとき、自分の自慢話ばかりしたり、相手の話に耳を傾けずに自分の話をし続けたりすると、相手から距離を置かれてしまいます。
一方的なやりとりは自己中心的な行動と見られてしまうため、注意が必要です。自己中心的な人は、その自覚がない場合が多いでしょう。
気付かないうちに、相手を傷つけたり失礼な行為をしたり、相手を遠ざけることをしています。その一方で、自分の気持ちには敏感で、孤独感を強く感じる人ともいえます。
まずは他者がどのような気持ちになるかを考え、自分の振る舞いを客観的に見られるようにしましょう。
4. 思考がネガティブになりがち
4つ目の理由は、「思考がネガティブになりがち」です。消極的な考え方によって、物事がうまくいかなかったり、ネガティブな行動につながったりしてしまいます。
例えば、誰かに話しかけようとしたときに「うまく話せなかったらどうしよう」と考えてしまったとします。すると実際には声をかけられずに、その場が流れてしまうでしょう。
また、ネガティブな思考は行動として現れるため、相手に良い印象を与えません。結果として周囲の人から距離を置かれるようになり、ひとりぼっちになってしまうのです。自分自身の思考が、ひとりぼっちを招く原因と言えます。
思考を変えていくのは簡単ではありませんが、小さなことからポジティブ思考に移れるよう意識しましょう。
ひとりぼっちを解決するには?あえて逆手に取る方法もアリ
学校でひとりぼっちになってしまった際、解決に向けて行動することももちろん良いのですが、「ひとりぼっちではなく、自分ひとりだけの時間である」とポジティブに考え、逆手に取ってしまう方法もあります。以下に例を挙げます。
- ・同じようにひとりぼっちの人を探す
- ・ひとりの時間を使って勉強や読書に集中する
- ・教室以外で授業を受けてみる
- ・熱中できる趣味やモノを見つける
- ・話しやすい人を探す
現在の状況を考慮しつつ、無理なく試せそうなものからトライしてみるといいでしょう。
1. 同じようにひとりぼっちの人を探す
1つ目は「同じようにひとりぼっちの人を探す」です。学校の中でひとりぼっちでいると、孤独を感じたりネガティブな思考が巡ったりしがちです。
しかし、実際にはひとりぼっちでいるのは自分だけではないことがあります。クラス替えや人間関係の変化によって、同じようにひとりぼっちでいる人がいるかもしれません。
周りの人とコミュニケーションを取るのは緊張しても、同じ境遇の人であればコミュニケーションがとりやすいでしょう。うまくきっかけが作れれば、ひとりぼっちを解決して友達になれる可能性もあります。休み時間や下校する際などに、声をかけてみてください。
2. ひとりの時間を使って勉強や読書に集中する
2つ目は「ひとりの時間を使って勉強や読書に集中する」です。学校の休み時間に友達といないと、周りからは「ひとりぼっちでかわいそう」と思われるかもしれません。しかし、自分だけのために時間を使えると考えることもできます。
「ひとりぼっちの時間は寂しい」という考え方ではなく、「ひとりでいるからこそできること」を探して勉強や読書に打ち込み、有意義な時間に変えてしまいましょう。教室にひとりでいるのが苦痛だと感じるのであれば、ひとりの空間を確保しやすい図書室や自習室を活用してみてください。
3. 教室以外で授業を受けてみる
3つ目は「教室以外で授業を受けてみる」です。ひとりぼっちになりがちな人の多くは、人と接するのが苦手な場合が多いです。そのため、クラスの大人数の中にいるのが苦痛になってしまう可能性があります。教室以外の居場所として、保健室や相談室などがあり、特定の先生や生徒とのコミュニケーションを通して、徐々にひとりぼっちから人との関わりを広げていけるでしょう。
また、相談室では先生から授業を受けられます。「教室にいないと先生から勉強を教えてもらえない」と思っている人は、相談室で授業を受けたいと相談してみてください。
保健室登校や相談室登校は、学校によっては出席日数に含まれます。出席扱いになるかどうかは、進路の選択をする際の重要なポイントになります。
4. ひとりぼっちだからこそ熱中できる趣味を見つける
4つ目は「ぼっちだからこそ熱中できる趣味を見つける」です。テレビやSNSなどで「ひとりカラオケ(ヒトカラ)」「ひとり焼肉」「ぼっち飯」「ソロキャンプ」など、ひとりぼっちで楽しむ行動を見聞きしたことはありませんか。ひとりぼっちでいても、何か熱中できる趣味があったり打ち込めるものがあったりすると、充実した時間を過ごせます。さらに、それが将来の仕事や得意なことにつながる可能性があります。
また、同じ趣味の人が近くにいれば、その趣味を通してコミュニケーションが活発にでき、仲良くなれるかもしれません。まずは自分が好きなことを見つけ、「推し」を作ってみてください。ひとりぼっちから脱却できるきっかけになるでしょう。
5. 話しやすい人を探してみる
5つ目は「話しやすい人を探してみる」です。人に話しかけるのは、慣れ親しんだ人でない限り、誰でも緊張するものです。
特に、学校のようにクラスが決まっている場合は、コミュニケーションのきっかけ作りができるかどうかが肝心です。まずは隣の席の人や雰囲気が柔らかい人など、自分が話しやすそうだと感じる人がいたら勇気を出して声をかけてみましょう。
一度きっかけが作れれば、そのあとのコミュニケーションも臆せず取れるようになり、ひとりぼっちから脱却できるかもしれません。
学校以外で自分の居場所を見つける方法
ひとりぼっちの人が学校以外に居場所を見つけられる場所として「習い事や塾」「通信制高校」などがあります。また、学校を休むことで新たな居場所を見つけられる場合もあるでしょう。
学校以外で自分の居場所を見つけることができれば、これまでひとりぼっちと感じていた状況に大きな変化を起こせるかもしれません。ここからは、学校以外の居場所を見つける方法について紹介します。
1. 習い事や塾などで居場所を探す
学校以外の居場所として、習い事や塾が挙げられます。クラスでは友達を作れずひとりぼっちでいる人も、場所が変わればそこでしか出会えない友達ができる可能性があります。
例えば、同じような進路先を目指す塾であれば、目標に向かって切磋琢磨できる友達と出会えるでしょう。また、習い事では同じような趣味を持っている人が集まるため、気の合う友達を見つけられる場合もあります。学校以外でのさまざまな出会いは、充実した人間関係につながるかもしれません。
2. 通信制高校に通ってみる
学校以外の居場所が見つかったとしても、登校日数が足りないと卒業要件を満たせない可能性があります。そのような場合は、登校日数が少なくても卒業を目指せる「通信制高校」を選択肢とするのもいいでしょう。毎日登校する必要がない通信制高校では、不登校という概念がなく、自身が興味を示すものを学びやすい環境があります。
通信制高校に通う人の多くは、不登校やひきこもり、慢性的な体調不良などの悩みを抱えています。自分と同じように、ひとりぼっちになってしまう悩みを抱えていた人もいるでしょう。お互いに悩みを打ち明け、励ましあえる仲間ができれば、かけがえのない友人ができるかもしれません。
「ズバット 通信制高校比較」では、実際に不登校やぼっちを経験したことで通信制高校に通い、「前向きになった」「友達ができた」という人の体験談やインタビューを掲載しています。同じようにつらい体験を乗り越えて元気に学校生活を送っている人がたくさんいますので、ぜひ参考にしてみてください。
>>生徒&先生の本音インタビュー
>>みんなの学校選び・スクールライフ体験談
3. 思い切って学校を休んでみる
学校に行かないといけないと感じ、気持ちが落ち込んでしまう場合は、思い切って学校を休むのも選択肢のひとつです。ひとりぼっちでいるとネガティブな思考が深まり、学校に行くこと自体がつらくなってしまう可能性があります。
落ち込んだ気持ちを回復させるためにも、学校を休んで距離を置くこともおすすめです。周りの目を気にしすぎないで、次に学校に行くための気力を補充しましょう。
回復した後に学校に行ってみるとこれまでとは見える景色が変わり、前向きに学校に向き合えるかもしれません。
つらいひとりぼっちに対処する3つの考え方
ひとりぼっちでつらい思いをするのを回避するためには、「消極的な考えをやめる」「相手の話に耳を傾ける」「相手の立場を考える」などの対処法が挙げられます。
他者と円滑な人間関係を築けるようにするには、根本的な考え方を変える意識を持つことが重要です。自分自身の考え方を変えることで、物事の捉え方も変わります。ここでは、ひとりぼっちへの対処法について、詳しく解説します。
1. 消極的な考えをやめる
1つ目は「消極的な考え方をやめる」です。消極的な考え方は、周囲の人々から距離を置かれてしまうことにつながります。どうしても消極的に考えてしまう場合は、意識的にポジティブな考えに切り替えていくとよいでしょう。
とはいえ、いきなり自分の考え方を真逆にするのは難しいものです。自分の身近な人や、好きな芸能人などで「こんな考え方ができるなんて素敵だな」という人がいないでしょうか。そのような人の言動を観察して、考え方を変え、真似する習慣をつけてみましょう。
どんなに小さなことでも構わないので、自分の行動や考え方が変わったなと感じることが増えてくれば、徐々に自信がついてくるはずです。ネガティブな考えをポジティブな考えへ変換できるようになれば、ひとりぼっちを脱却するきっかけを作れるかもしれません。
2. 相手の話に耳を傾ける
2つ目は「相手の話に耳を傾ける」です。コミュニケーションがとにかく苦手な人は、相手に話しかけるときに何を話したらいいか悩む場面も多いでしょう。
話しかけるきっかけが作れても、話が展開できなければ自信を失ってしまいます。コミュニケーションが上手く取れない人は、まず相手の話を聞く姿勢を意識しましょう。
相手に興味を向ければ、その人の話を聞きたいと意識しやすくなります。自分から何か話さなければと思わず、関心を向けていると伝わる「聞き上手」になると好印象です。
そうすれば、相手に嫌な思いをさせずに円滑なやりとりができるようになります。相手の話を受け入れれば好感を得やすくなり、信頼関係を構築できるでしょう。
3. 相手の立場で物事を考える
3つ目は「相手の立場で物事を考える」です。ひとりぼっちになりがちな人の特徴のひとつに、自己中心的で相手の話を聞かないことが挙げられます。
自分の話ばかりで一方的なコミュニケーションを取る人は、「この人と話しても面白くない」と相手から敬遠されかねません。また、自己中心的な振る舞いをしていると、直接関わっていない人からの印象も悪くなってしまいがちです。
これらの問題からひとりぼっちになるのを回避するために、相手の立場で物事を考えるように意識しましょう。相手の立場を考えた言動をできるよう、気を配って物事を考える癖をつけると、周りもその変化に気付きます。
その結果として、自己中心的な人という印象から優しい人と思われるようになり、次第に周りに人が戻ってくるでしょう。相手に対して優しい言動をすることが、ひとりぼっち回避のために必要な考え方と言えます。
学校でのひとりぼっちを相談できる窓口
学校内にひとりぼっちでいて、悩んでいるときに相談できる窓口がたくさんあります。うまく活用すれば、寂しさや不安について相談できると同時に、ひとりぼっちの解決方法を見つける糸口となるでしょう。
「他人に相談しても何も変わらない」と思っている人も多いかもしれません。しかし、まずは自分の考えや悩みを打ち明けることで、自分自身の思考を整理でき、変化につなげることができるはずです。ここでは、それぞれ相談窓口の特徴について紹介します。
■公的相談窓口
公的相談窓口は、地域や専門機関で相談できる窓口を指します。相談相手はカウンセラーや教員などで、子供の悩みに詳しい人が対応してくれるため、問題解決につながりやすいでしょう。代表的な公的相談窓口は、以下の通りです。
- ・学校(担任、スクールカウンセラー)
- ・教育相談室(教育相談員、発達相談員)
- ・ひきこもり地域支援センター(社会福祉士、臨床心理士)
- ・児童相談所(カウンセラー)
- ・教育センター
- ・民間の不登校支援団体
また、直接相談しに行くのは抵抗がある人に向けて、電話相談やLINE相談を受け付けている窓口もあります。以下は、子供からの相談を全般的に受け付けている場所です。
ひとりぼっちは悪いことではないけれど、状況を変えるのは自分次第
ひとりぼっちでいるのは、決して悪いことではありません。学校でひとりぼっちでいても、学校以外の場所で新しい仲間ができれば充実した人生につながるからです。
また、ひとりでも熱中できる趣味や目標があれば、それは自分にとって価値のあるものとなります。しかし、学校でひとりぼっちになっている人の大半が、それを恥ずかしいと思って誰かに相談しづらいと感じ、「誰かに話してもしょうがない」とネガティブに考えてしまうこともあるでしょう。
ひとりぼっちでいる寂しさやつらさを抱えているのであれば、その悩みを誰かに相談することで解決に向かう可能性があります。電話相談やSNSの相談など、気軽に話せる窓口もその方法のひとつです。
悩みを打ち明けると、思わぬ解決方法と出会い、ひとりぼっちを解消できるかもしれません。ひとりで抱え込まずに相談して、前向きに人との関係づくりについて考えていきましょう。