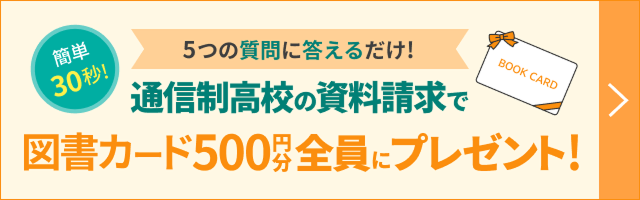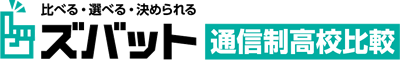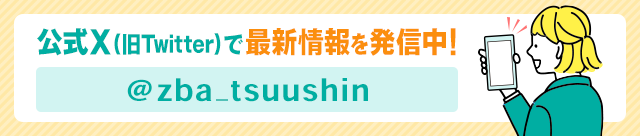学校に行きたくないときの対処法とは?NG行動や相談先も紹介
公開日:2017年08月28日 更新日:2025年02月10日

学校に行きたくないと悩む子どもをもつ保護者の中には、「このまま不登校になってしまうのではないか」「将来に影響するのではないか」と不安を抱える人もいるでしょう。 子どもが学校に行きたくないと思う背景には、学業の悩みや人間関係の不安などさまざまな理由があります。そのため、子どもの意思を尊重して慎重に解決策を見つけることが大切です。 この記事では、子どもが学校に行きたくないと感じる理由やその対処法、避けるべき行動などを解説しているので、ぜひ参考にしてください。
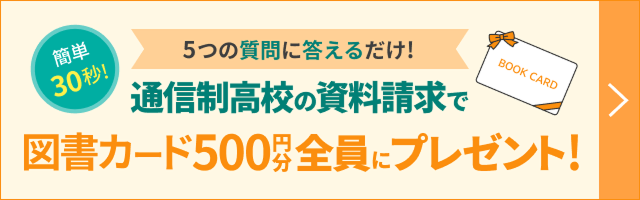
学校に行きたくない理由
子どもが学校に行きたくないと感じる理由はさまざまです。文部科学省の調査によると、中高生の主な不登校理由は以下の通りでした。
| 不登校理由 | 中学生 | 高校生 |
|---|---|---|
| やる気が出ない | 32.2% | 32.8% |
| 生活リズムの不調 | 22.1% | 26.7% |
| 不安や抑うつの状態 | 23.4% | 16.7% |
| 学業不振 | 15.5% | 15.4% |
| いじめ | 1.0% | 0.9% |
| いじめを除く友人関係 | 14.4% | 11.0% |
| 教職員との関係 | 2.1% | 1.6% |
| 親子関係 | 9.6% | 6.8% |
| 家庭生活の変化 | 5.9% | 5.0% |
| 学校生活になじめない | 6.5% | 8.0% |
出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」をもとに作成
不登校の理由として最も多い回答は「やる気が出ない」でした。「生活リズムの不調」や「不安・抑うつ状態」などと合わせると、心身の不調を理由として挙げている人が75%以上にのぼることが分かります。
また「親子関係」「家庭生活の変化」といった家庭環境にも不登校の要因があり、「学業不振」や「人間関係」など、学校生活だけが原因とはかぎらないことがわかります。
中学生・高校生が学校に行きたくないと感じる理由については、以下の記事も参考にしてください。
学校に行きたくない子どもに親ができる対処法
子どもが学校に行きたくないと言った場合に、親がとるべき対処法は以下の通りです。
- 子どもの気持ちに寄り添う
- 休んでもよいと伝える
- 生活リズムを整える
- 学校に相談する
- 家庭環境を見直す
- 勉強以外のやりたいことを支援する
- 学校以外の学習環境を整える
子どもの気持ちに寄り添う
まずは、子どもの気持ちを受け入れましょう。学校に行きたくない理由が、大人にとっては些細な問題だったとしても、子どもにとっては重要な問題であることがあります。頭ごなしに否定するのではなく、子どもに寄り添うことが大切です。
「つらかったね、よく我慢したね」と共感し、ありのままを受け入れることが子どもの安心感につながります。
子どもが頼れるのは親しかいません。だからこそ、子どもを急かさずに前向きな気持ちになるまで待ってあげることも大切です。
何が原因で学校へ行くことがツライのか、いま子どもが置かれている状況に耳を傾け、解決策を一緒に考えてみましょう。
休んでもよいと伝える
学校を休んでもよいと伝えることも大切です。無理やり登校させることは、子どもをさらに追い込むことにつながります。
例えば、子どもが以下のような兆候が見られる場合は、注意しましょう
- 週1回以上、保健室など教室以外の場所を利用している
- 登校前になると、頭痛や吐き気などの身体的な症状を訴える
- 寝つけなかったり、夜中に何度も目覚めたりする
- 遅刻や早退が増えた
万が一、不登校になっても学習を続ける方法はほかにあります。子どものことを第一に考え、無理をさせないことが大切です。
生活リズムを整える
決まった時間に起床・就寝できるように声をかけたり、食事の時間を固定したりするなど生活リズムを崩さないようサポートをしましょう。生活リズムが乱れると、体調を崩したり、精神的に衰弱したりする要因になりかねません。特に、休み明けの月曜日は生活リズムが乱れがちです。
学校に行かなくなった場合でも規則正しい生活を送るために、以下のような点を意識するとよいでしょう。
- 早寝早起きを習慣づける
- 朝ごはんを食べるようにする
- 1日8時間以上の睡眠時間を確保する
- テレビやゲームの時間を決める
- 勉強する時間を決める
日頃から生活リズムを整えておくことで、学校に行きたくなった際にも、スムーズに学校生活に戻りやすくなるでしょう。
学校に相談する
学校と連携することで、学校に行きたくない原因がわかり、解決につながることがあります。
例えば、人間関係が原因の場合、子どもが理由を話しづらい場合があります。学校と連携しておくことで、学校での様子を調べてもらうなどの協力を得られるでしょう。
授業についていけていないことが原因だった場合も、家庭内だけで解決するのは難しいと考えられます。担任教師に相談することで、学習方法の改善など、具体的な解決策を検討することができるでしょう。
また、勉強の遅れや出席数に不安があると、焦りからますます心身が衰弱してしまうことも考えられます。どうすれば進級・卒業を目指せるかについても学校に相談してみましょう。
- いまの時期はどこを勉強しておくべきか
- 進級に必要な出席日数はどのくらい必要か
- 教室に通わずに学ぶ方法はあるか
- 進級や卒業のためにはどういった対策が考えられるか
- どういった進路が考えられるか
相談をすることで、進級・卒業への焦りや不安を和らげることが期待できます。また、助言をもらうことで保護者の安心感にもつながるでしょう。
家庭環境を見直す
家庭環境に問題があれば見直すことも大切です。以下のような点に心当たりがないかチェックしましょう。
- 親の過保護・過干渉
- 親の無関心・放任主義
- 家庭内の不和
過保護・過干渉になっている場合、子どもは親の期待に応えようとし、プレッシャーを感じることがあります。
また、無関心・放任主義である場合も気をつけましょう。「がんばっても褒めてもらえない」と感じて、モチベーションや自己肯定感の低下につながる可能性があります
さらに、家庭内の不和は心的ストレスに直結します。家族と気軽に会話できる場所を作るなど、居心地が良いと感じる家庭環境づくりを心がけましょう。
勉強以外のやりたいことを支援する
勉強以外で「やりたい」「がんばりたい」と思えることを伸ばすことも大切です。好きなことや得意なことに取り組むことで自信がついてきます。
積極的に取り組めるものに出会うことで、新たな友達ができるなど、人間関係が広がることもあるでしょう。友人ができることで、学校へまた行きたいと思えるようになるかもしれません。
学校以外の学習環境を整える
学校には行きたくないけれど、勉強する意思がある場合は、学校以外の学習環境を設けてもよいでしょう。
- フリースクール
- オンライン教育サービス
- 通信制高校、通信制高校の中等部
フリースクール
フリースクールとは、学校になじめない小学生・中学生・高校生を対象にした民間の教育施設です。
子どもが安心して過ごせる場所の提供や、自信をもって学び続けるための支援、自立した生活を送れるようにするためのサポートを行っています。
学習活動だけでなく生活相談や心のケアにも対応してくれます。
オンライン教育サービス
オンライン教育サービスとは、インターネットを通じてリモートで教育を受けられるサービスです。
オンライン教育サービスを利用すれば、学校へ行かなくても自宅で学習を続けることが可能になります。
また、サービスによってはゲームやメタバース空間などを活用した教育を行っている場合もあります。楽しく勉強ができれば、学習意欲が高まり、学校へ行く意欲にもつながる可能性があるでしょう。
通信制高校/通信制高校の中等部
高校生であれば、通信制高校という選択肢もあります。通信制高校は自宅学習が基本のため、自分のペースで学習を進めることができます。
通信制高校は、自身の状況に合わせたカリキュラムを編成できるため、進路や目的に合わせて学習を進められます。また、自宅学習がメインなので、登校日数が少なく子どもの負担を減らせるでしょう。
中学生の場合は、通信制高校の中等部という選択肢もあります。
通信制高校の中等部では、学習以外にも専属のカウンセラーに悩みを相談したり、全日制高校への進学相談をしたりといったサポートも受けられたりします。また、学校によっては中学校の出席日数にカウントできたり、通信制高校への内部進学を保証したりしているケースもあります。
通信制高校について詳しく知りたい人は、『通信制高校とは?カリキュラムや全日制との違いをわかりやすく解説!』も参考にしてください。
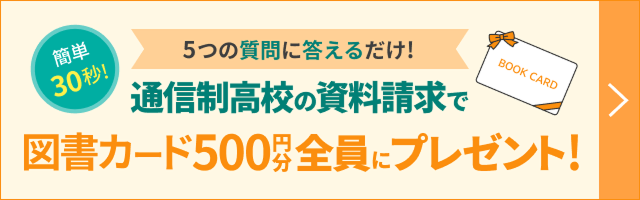
対処する上で注意したいこと
子どもが学校に行きたくないと打ち明けた際は、以下の点に注意しましょう。
- 親や家庭だけで問題を抱え込まない
- 子どもからの相談を他人任せにしない
- 必要以上に自分を責めない
親や家庭だけで問題を抱え込まない
学校や専門機関に相談し、親や家庭だけで問題を抱え込まないようにしましょう。
例えば、発達障害や精神的な病気が原因の場合、家庭だけで解決するのは簡単ではありません。専門機関や医療機関に相談することで解決策が見つかる可能性が高まります。
子どもの状況によって相談先は異なります。相談窓口については後述するので、参考にしてください。
子どもからの相談を他人任せにしない
子どもへの対応を学校やカウンセラーなど他人任せにしないように気をつけましょう。
「仕事が忙しいから」「対応がわからないから」などの理由で、先生やカウンセラーに任せきりにしてしまうことがあるかもしれません。しかし、他人任せにすると、子どもは「親から大切にされていない」と感じてしまう可能性があります。
子どもの心情に寄り添い、向き合ってあげることが大切です。
必要以上に自分を責めない
親が自分自身を責めて思い悩んでも、問題解決にはつながりません。子どもが学校に行きたくない理由が家庭問題だった場合は、ショックで自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。
家庭の問題で子どもにストレスをかけてしまったのは事実かもしれませんが、自身を責めたところで状況は解決しません。子どもが抱える「学校へ行きたくない気持ち」と向き合い、問題を解決できるように行動する必要があります。
学校行きたくない子どもへのNG行動
子どもが学校に行きたがらない場合は、対応方法に注意が必要です。親が避けるべき行動について解説します。
- 否定的な言葉を投げかける
- 理由を問い詰める
- 無理に学校に行かせる
- 親の価値観を押しつける
否定的な言葉を投げかける
感情的になって、子どもに「甘えるな」「わがままを言うな」などの否定的な言葉をかけることは避けましょう。
子どもにとって「学校に行きたくない」と打ち明けることは勇気のいる行動です。勇気を出して打ち明けたのに、頭ごなしに否定されてしまうと、子どもはさらに追い詰められてしまいます。
打ち明けた時点で、子どもの心は限界を迎えている可能性もあります。冷静に受け止め、子どもの言葉に耳を傾けましょう。
理由を問い詰める
「何があったの?」「なぜ学校に行けないの?」など理由を問い詰めることも禁物です。しつこく問い詰めてもプレッシャーを与えるだけで解決になりません。
学校に行きたくない理由を話したがらないのは、次のような理由が考えられます。
- 理由を親に話したくない
- 学校のことを考えるだけでつらい
- 自分でも理由がよくわからない
学校に行きたくない理由についてしつこく聞かれると、責められていると感じてしまいます。また、結論を急ぐと気持ちがまとまらず、子ども自身が混乱してしまう可能性もあるでしょう。
話したくなったら自分から話してくれると信じて、そっと見守ってあげるのも手段の1つです。子どもの様子を見て、今後のことも含めた前向きな話をしてみると良いでしょう。
無理に学校に行かせる
無理に学校に行かせることも避けるようにしましょう。
子どもが学校に行きたくないと思う理由はさまざまです。場合によっては時間が解決してくれることもありますが、問題が解決していない状態で登校させても、本人が苦痛なだけで余計に負担をかけてしまいます。
無理強いすることで、学校への恐怖心や嫌悪感が増し、余計に学校に行けなくなることも考えられます。
子どもの様子を見ながら、徐々に原因を探り、解決方法を一緒に考えていきましょう。
親の価値観を押しつける
自分の価値観を子どもに押しつけるのも禁物です。一般的な価値観を押しつけてしまうと、子どもをさらに追い込むことになりかねません。
例えば「勉強についていけなくなったらどうするの?」「受験できなくなったらどうするの?」などと言いたくなることもあるでしょう。しかし、現実を押しつけても、逆効果になる可能性があります。
価値観を押しつけるのではなく、子どもの気持ちに寄り添ってあげることが大切です。
子どもの不登校、メンタルケアに関する相談窓口
不登校を親だけで解決するのは簡単ではありません。家庭で抱え込まず、下記のような専門機関に相談するのがおすすめです。
- スクールカウンセラー
- 教育センター(教育相談センター)
- 教育支援センター(適応指導教室)
- こども家庭センター
- ひきこもり地域支援センター
- 保健所や保健センター
- 精神保健福祉センター
- 発達障害者支援センター
- 不登校の親の会
スクールカウンセラー
「スクールカウンセラー」とは、学校で子どもの心のケアや精神的なサポートをする専門家です。
スクールカウンセラーは、いじめの深刻化や不登校児童の増加を受けて、学校でカウンセリングできるように配置された専門家です。子どもだけでなく、保護者もカウンセリングの相談ができます。
教育センター(教育相談センター)
「教育センター(教育相談センター)」とは、都道府県や市区町村が設置している子どもの教育に関する相談窓口です。
利用対象は高校までの子どもと保護者で、不登校・いじめ・発達障害などの教育場面における悩みを相談することができます。
不登校相談会や学校復帰に向けたセミナーなどを実施しているところもあります。
教育支援センター(適応指導教室)
「教育支援センター(適応指導教室)」は、不登校児童・生徒の学校復帰を支援することを目的としています。
子どもだけでなく、保護者に向けたサポートも行っています。また、児童生徒の在籍校と連携を取りながら、個別カウンセリングや集団指導を行っているところもあります。
こども家庭センター
「こども家庭センター」は、子ども・子育て世帯・妊産婦を包括的に支援する公的施設です。医療・福祉・保育・教育などの多方面から支援を行っています。
従来の市区町村には、母子健康を担う「子育て世代包括支援センター」と児童福祉を担う「子ども家庭総合支援拠点」がありましたが、2024年4月施行の改正児童福祉法により、ふたつの機能を統合し「こども家庭センター」が新設されました。
教育委員会・学校・放課後児童クラブなどの関係機関と協力し、民間・地域一体となった支援体制を構築しています。
ひきこもり地域支援センター
「ひきこもり地域支援センター」とは、行政が運営する、ひきこもりに特化した相談窓口です。
すべての都道府県・指定都市にあり、社会福祉士・精神保健福祉士などの資格を有するコーディネーターが相談支援を行います。
また、地域における関係機関とのネットワーク構築や、ひきこもり支援に関する情報を幅広く提供するなど、地域におけるひきこもり支援の拠点としての役割も担っています。
精神保健福祉センター
「精神保健福祉センター」は、精神障害を抱える人の福祉や精神的な健康の向上を図ることを目的とする機関です。
精神保健福祉法によって、各都道府県および政令指定都市に設置することが定められており、心の健康や精神医療、社会復帰などに関する相談を実施しています。
発達障害者支援センター
「発達障害者支援センター」は、発達障害のある人への総合的な支援を行うことを目的とした専門機関です。都道府県知事等が指定した社会福祉法人・特定非営利活動法人などで運営されています。
発達障害のある人とその家族が、安心して生活を送れるように、保健・医療・福祉・教育・労働などの関係機関と連携してサポートを行います。
学校生活や日常生活におけるさまざまな困りごとの相談ができ、必要に応じて、医療機関や福祉施設などの関係機関を紹介してもらえます。
不登校「親の会」
不登校「親の会」とは、不登校の子どもをもつ親同士のコミュニティです。
不登校の子どもをもつ親は、だれに相談したらよいかがわからず、一人で抱え込んでしまう場合があります。同じ悩みをもつ親同士で情報交換したり、悩みを相談したりすることができます。
家での子どもの過ごし方など、不登校の保護者同士だからこそできる話ができ、参考になることも多いでしょう。
地域のフリースクール・学習機関・医療機関について、周りの利用者の声を聞ける点もメリットと言えます。
全国に400以上の団体があり、セミナーや学習会が実施されることもあります。
まとめ
子どもが「学校に行きたくない」というときの理由はさまざまです。頭ごなしに否定をしても解決はしないため、子どもの気持ちに寄り添い、冷静に対処することが大切です。
子どもの現状を受け入れて、気持ちの回復を待ちましょう。落ち着いた段階で子どもと話し合い、学校と連携したり、第三者に相談したりといった行動をとるようにしましょう。
学校に行きたいけど行けない、という人もいるかもしれません。通学せずに学習したい場合は、通信制高校や通信制高校の中等部などを検討してもよいでしょう。
自分に合った通信制高校を探したい方は、通信制高校選びの無料診断を利用してみてください。5つの質問に回答するだけでおすすめの学校タイプや通学スタイルがわかるため、効率的に学校探しができます。