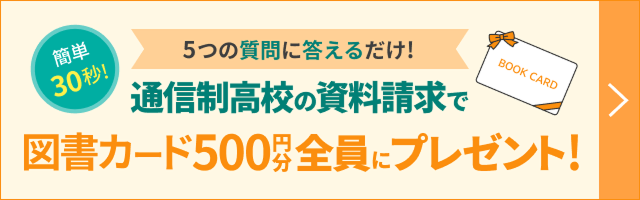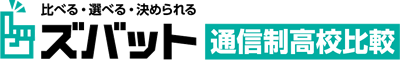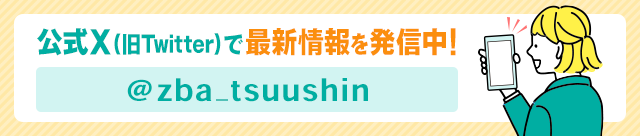不登校の中学生の進路は?進学しやすい高校や進路を選ぶ際の注意点
公開日:2021年03月19日 更新日:2025年03月21日

不登校の中学生を持つ親にとって、子どもの進路についての悩みは切実です。「中学を卒業できるのか」「高校に行けるのか」という不安を抱えている人もいるでしょう。中学で不登校でも、高校に行くことは可能です。この記事では、不登校の中学生でも進学しやすい高校や、進路を選ぶ際の注意点について解説します。
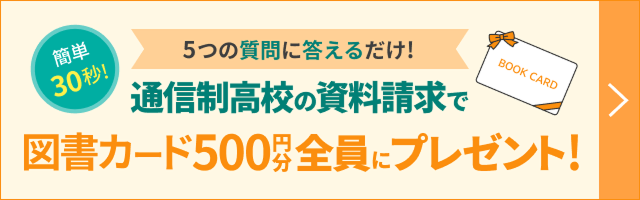
不登校でも中学卒業できる?
公立中学校では、年齢主義に基づいた義務教育制度を採用しています。年齢主義とは、生徒の年齢に基づいて学年を決める仕組みです。
これにより、成績や出席日数にかかわらず、同じ年齢の生徒が同じ学年に在籍することが保証されています。
したがって、不登校で出席日数が少なくても、基本的には留年することなく卒業できます。
不登校の中学生の進路
留年することなく卒業できるとはいえ、不登校の中学生にとって進路選択は重要なテーマです。
全日制高校、通信制高校、定時制高校、高卒認定試験、就職など、さまざまな選択肢があります。それぞれの選択肢には特徴があり、子どもに合ったものを選ぶことが大切です。
通信制高校
通信制高校は、毎日通学する必要がなく、自宅でインターネットを通じて授業を受けながら単位を取得し、高卒資格を取得するための学校です。 授業カリキュラムは全日制の学校とほぼ同じで、授業でつまずいたところがあれば、先生からサポートやアドバイスが受けられます。
通信制高校は、基本的に登校する必要がないため、学校に行くことに抵抗のある人にとってストレスなく学習できる環境と言えます。
定時制高校
定時制高校は、全日制高校より1日の授業時間が短く、昼間や夜間に授業を行う高校です。
昼間二部制、昼夜間三部制など学校によってさまざまな選択肢があり、生徒のスケジュールに合わせて柔軟に通学できます。そのため、昼間に仕事をしている人や、ほかの事情で昼間に時間が取れない人も通学が可能です。
全日制高校
全日制高校は、毎日通学する必要があり、日中に授業が行われる一般的な高校の形態です。授業時間は朝から夕方までで、部活動や学校行事も行われます。
中学で不登校だったとしても、入学条件を満たしていれば、全日制高校への進学は可能です。
昨今では、「不登校枠」という不登校の生徒に配慮した選考方法を用意している学校もあります。
不登校の生徒向けの高校
都道府県によっては、不登校の経験がある生徒向けの高校を設置している場合があります。
例えば、東京都のチャレンジスクールやエンカレッジスクールは、不登校などが原因で、小・中学校で十分に能力を発揮できなかった生徒を対象としています。チャレンジスクールは定時制、エンカレッジスクールは全日制の高校です。
不登校を受け入れる高校は、地域によって名称や制度が異なり、神奈川県のクリエイティブスクールやフレキシブルスクール、埼玉県のフロンティアスクールなどがあります。
高等専修学校
高等専修学校は職業訓練や技術教育に重点を置いている学校です。高校卒業と同等の資格を取得できます。
「高等専門学校」や「専門学校」と間違えやすいですが、対象者や得られる資格に違いがあります。
| 高等専修学校 | 専門学校 | 高等専門学校 | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 中学卒業 | 高校卒業/高卒認定 | 中学卒業 |
| 在籍年数 | 1~3年 | 1~4年 | 5年 |
| 得られる資格 | 高卒資格 | 専門士/高度専門士 | 準学資 |
高等専門学校(高専)
高等専門学校で学べる分野は、工業と商船の2分野です。これらの分野で即戦力になれる技術者を養成することが目的の学校です。
卒業に5年かかりますが、卒業後の就職率が高いことは高専の特徴の1つです。また、3年次を修了すると、大学入試資格が得られるため、進路変更をして大学進学を目指すことも可能です。
高卒認定試験
高卒認定試験は、高校を卒業していなくても、大学や専門学校へ進学する資格を得ることができる試験です。
高卒認定試験に合格すれば、高等学校卒業と同等の学力を持つことが証明されます。ただし、高校を卒業しているわけではないので、大学等へ進学しない場合は、
最終学歴は中卒となります。
その他(就職・留学など)
進学だけが選択肢ではありません。
高卒や大卒と比べると、選択肢が減ってしまいますが、中卒で正規雇用を募集している企業もあります。
最初から正社員でなくても、アルバイトで経験を積み、正社員登用を目指したり、独立を目指したりすることも可能です。
また、留学もひとつの選択肢です。留学は、異なる文化や価値観に触れることで、自己成長や新たな視点を得る機会となります。特に、日本での学校生活が合わなかった生徒にとって、リスタートの場として有効です。
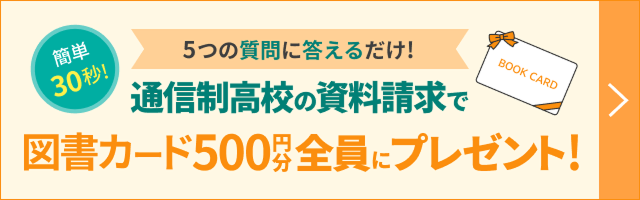
不登校だと全日制公立高校への進学は難しい?
不登校の中学生が全日制公立高校への進学を希望する場合、ハードルが高くなる可能性があります。
全日制公立高校の入試においては、出欠状況や内申点も加味されます。そのため、不登校期間が長くなると出席日数が不足したり、内申点が低くなったりして、入試で不利になることがあります。
しかし、先述の通り、不登校枠を設けている学校や、不登校の生徒向けの学校も増えてきています。こうした学校を受験することで、不登校でも全日制の公立高校に進学できる可能性は高まるでしょう。
不登校でも進学しやすい高校
不登校から全日制の公立高校への進学は、一定の難しさを伴います。特に中3時点で不登校の場合、進路を選ぶ際には、出欠状況や内申点の影響は念頭に入れておく必要があるでしょう。
一方、私立高校や定時制高校、通信制高校は、不登校でも進学しやすくなっています。
私立高校
私立高校の一般入試では、ほとんどの学校が、出欠状況や内申点を考慮しません。
内申点を加味する学校もありますが、学力検査を重視する傾向があるため、公立高校と比べると不登校でも不利になりにくいでしょう。
不登校枠のある高校
不登校枠とは、不登校経験がある生徒のために配慮された高校受験の選考方法のことです。欠席日数や内申点が不利に働かないように、合否判定に際してそれらの記録を柔軟に取り扱ったり、面接を重視したりする措置を取るというものです。
ただし、不登校の生徒に対して定員を設けているわけではなく、あくまで、不登校の生徒に配慮した選考方法が実施されるというものです。そのため、不登校の生徒の合格を約束するものではありません。
また、都道府県によって制度内容が異なるため、教育委員会のWebサイトなどで確認するようにしましょう。
定時制高校
定時制高校の入学試験も、出欠状況や内申点はあまり考慮されません。
定時制高校は、必ずしも不登校が行く高校というわけではなく、全日制高校を中退した人や社会人など、あらゆる人を受け入れています。
そもそも、事情があって全日制高校に通えない人を対象とした高校のため、不登校経験のある生徒も進学しやすくなっています。
通信制高校
通信制高校の入学試験は、生徒に勉強する意思があるかどうかを見るために行う場合がほとんどです。 そのため、出席日数や内申点が合否に影響を与えることはありません。
また、文部科学省の調査によると、通信制高校に通う生徒の約半数が、小・中学校や前の高校で「不登校の経験がある」ことがわかっています。不登校の経験がある生徒が進学しやすい高校と言えます。
通信制高校への進学については、『中学で不登校でも高校進学を諦めない!通信制高校という選択肢のメリットは?』を参考にしてください。
不登校の中学生の進路を選ぶ際の注意点
不登校の中学生の進路を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です。
子どもの意思を尊重する
不登校の中学生の進路を選ぶ際には、子どもの意思を尊重することが大切です。親の常識を押し付けたり、親が一方的に決めたりするのではなく、子どもの意見をしっかりと聞き入れましょう。
進学先や将来の職業について、さまざまな可能性を模索し、その選択肢が子どもの希望に合っているかを親子で話し合いましょう。
また、子ども自身が興味を持っている分野や、得意なことについても話し合い、子どもが自分の未来に対して主体的に関わる機会を提供することも重要です。
結論を急がない(子どもとじっくり話す)
不登校の中学生の進路を考えるとき、結論を急がず、子どもとじっくり話すことが重要です。
焦りや不安に駆られて早急に進路を決定すると、子どもにとって最適な選択肢を見過ごす可能性があります。
子どもの気持ちや将来のビジョンを尊重するために、子どもが自分の気持ちや考えを自由に話せる環境を整えましょう。親は聞き役に徹し、共感と思いやりを持って接することが重要です。
最終的な決定を急がずに、時間をかけて十分な情報収集を行い、慎重に選択肢を検討することが、子どもにとって良い進路につながります。
担任やスクールカウンセラーと相談する
不登校の中学生の進路を選ぶ際には、担任やスクールカウンセラーと相談することも重要です。
担任は生徒一人ひとりの学習状況や性格を把握しており、最適な進路について具体的なアドバイスを提供してくれます。また、スクールカウンセラーは子どもの心理的な状態を踏まえながら、適切なサポートを行ってくれます。
親子だけではない、第三者の意見を聞くことで、気持ちや考えを整理するきっかけにもつながります。
専門機関や支援機関に相談する
専門機関や支援機関に相談することで、適切なアドバイスや情報を得ることができ、不登校の中学生の進路選択がスムーズになります。
以下のような機関がサポートを提供しています。
- 教育支援センター:不登校の子どもの学校復帰を支援する相談窓口。
- 教育相談所:不登校や進路、学習など、教育に関するさまざまな問題について相談を受ける機関。
- フリースクール:不登校の子どもが通うことのできる民間の教育機関。
- 子ども家庭支援センター:18歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談に対応する窓口。
- 精神保健福祉センター:精神的な健康問題に対するサポートを行う機関。
- 児童相談所:18歳未満の子どもに関するあらゆる相談を受け付け、支援を行う機関。
- 引きこもり地域支援センター:引きこもりに特化した相談窓口。
まとめ
不登校の中学生の進路選択には、多様な選択肢が存在します。通信制高校、定時制高校、全日制高校、不登校生徒向けの高校、高等専修学校や高等専門学校など、それぞれの特徴を理解し、子どもに合った進路を探してください。
また、親としては子どもの意思を尊重し、結論を急がずにじっくり話し合うことが大切です。担任やスクールカウンセラー、専門機関とも相談し、最適な進路を見つけるためのサポートを惜しまないようにしましょう。
下の記事では、不登校のサポートが手厚い通信制高校について紹介しています。参考にしてください。