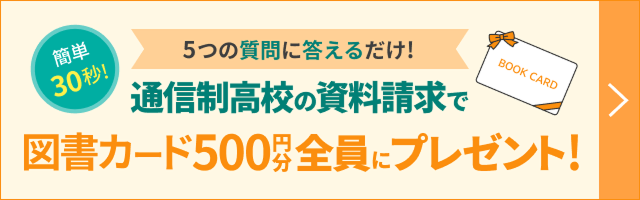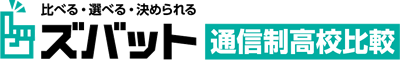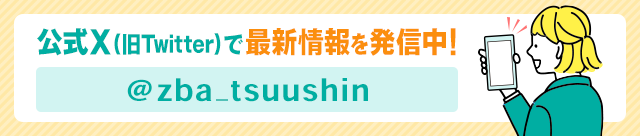高校で留年しそう・・・留年の基準、救済措置、その後の進路について解説
公開日:2021年09月30日 更新日:2025年02月07日

高校を留年しそうだとわかったら誰もが不安に感じます。そうなったときこれからどのような進路が選べるのでしょうか。この記事では、高校における留年の基準と現状、留年のデメリットとメリットを解説し、留年したあとに選べる進路の選択肢を紹介します。
単位制の通信制高校なら留年なし!
【簡単30秒】自分にぴったりの学校を診断!高校の留年とは
高校の留年とは、正式には「原級留置」といい、生徒が次の学年へ進級できず、新年度も同じ学年にとどまることを意味します。
例えば1年生で留年すると次年度も1年生となり、3年生で留年した場合は卒業できずに3年生として過ごすことになります。
高校留年の現状
文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によると、令和5年度では8,990人の高校生が留年しています。全国の国公私立高校に在籍しているのは292万5,515人なので、全体の約0.3%が留年している計算になります。
高校で単位を取得するための基準
高校で留年するかどうかは「単位」の取得状況によって決まります。単位とは、科目ごとに定められている、学業の修了に必要な授業量のことです。
各単位を得るためには、科目ごとに「成績」「出席日数」の基準を満たすことが欠かせません。
成績
定期テストにおいて、各科目の基準点を下回る成績を取ると、単位が与えられないことがあります。いわゆる「赤点」と呼ばれる状態です。
つまり、留年しないようにするためには、定期テストで赤点を取らないようにすることが大切です。
ただし、赤点を取ったからといって留年がすぐに決定するわけではなく、補習授業や再試験が行われるケースが多いです。補習授業に出なかったり、同じ科目で何度も赤点を取ったりすると、留年する確率が高くなります。
出席日数
出席日数の基準は、学校や自治体ごとに定められているものの、3分の1の出席を目安としています。出席日数は、単に登校した日数ではなく、科目ごとに計算される授業時間の出席が必要です。
例えば、数学の授業を欠席した翌日に国語の授業を受けたとしても、国語の授業の出席日数にカウントされるだけで、数学の授業の欠席分を補うことはできません。
また、学校によっては遅刻3回で欠席とみなされるケースもあるため、遅刻にも気をつけましょう。
留年しないための救済措置
一般的に高校では、留年する恐れがある生徒に対する救済措置が設けられます。例えば、追試や補修、レポート提出などがあります。
また、出席日数が基準に満たない場合には、長期休暇中に補習授業を受けることで、不足分を補うことも可能です。
ただし、必ずしも救済措置が設けられているわけではありません。留年の不安がある場合には、早い段階で学校に相談するのが望ましいです。
留年してしまった場合の選択肢
高校を留年してしまった場合は、以下の選択肢があります。
- 在籍中の高校で同じ学年をやり直す
- 別の全日制高校へ転入する
- 通信制高校へ転入する
- 定時制高校へ転入する
- 高卒認定試験を受ける
- 就職する
在籍中の高校で同じ学年をやり直す
在籍中の高校で同じ学年をやり直して単位を取得すれば卒業できます。転校や退学といった手続きが不要で、環境が変わることによる負担もありません。
ただし、留年すると元のクラスメイトが上級生となり、年下の生徒がクラスメイトになるため、馴染めなかったり、元同級生と顔を合わせるのが苦痛になったりすることもあります。
また、元の同級生よりも進学や就職のタイミングが遅れることになります。
別の全日制高校へ転入する
別の全日制高校に転入し、人間関係や環境を新しくすることで、学習への意欲がわいてくることもあるでしょう。
ただし、全日制高校は転入条件が厳しく、手続きが複雑な傾向にあります。また、決まった時間に通学して授業を受けなければならないため、全日制の学習スタイルが合わずに留年になってしまった人にとっては難しいかもしれません。
通信制高校へ転入する
通信制高校では、提供された教材を用いて自宅で学習し、高等学校課程に必要な単位を習得できます。時間や場所を選ばずに学習できるため、通学せずに自宅に居ながらでも学べる点がメリットです。
体調不良などの理由で出席日数が足りずに留年してしまった人も、通信制高校ならば無理なく自分のペースで学習を進められます。また、他人と顔を合わせるのが苦手な人にも向いています。
ほとんどの学校が入学時に試験がなく、書類審査と面接のみなので、転入のハードルが低い点も魅力です。
通信制高校への転入については、『通信制高校への編入と転入の違いを解説!注意点から判断ポイントまで紹介』も参考にしてください。
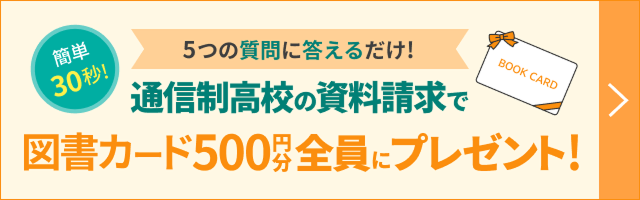
定時制高校へ転入する
定時制高校では、昼間または夜間の決められた時間に学校へ通います。一日中学校で勉強するのではなく、自分の生活スタイルに合う時間帯で学習を進めたい人におすすめです。
また、定時制高校には、働きながら通学する生徒もいるため、年齢差が気になりにくいでしょう。
しかし、学校に通うことが苦手という人にとっては、毎日の通学が負担になる恐れもあります。
定時制高校については、『定時制高校とは?全日制との違いをわかりやすく解説!』も参考にしてください。
高卒認定試験を受ける
高卒認定試験の正式名称は「高等学校卒業程度認定試験」で、合格することで高卒者と同等の学力があると認定され、高卒資格が必要な大学や専門学校を受験できます。
高校を留年したものの大学や専門学校へ進学したい場合、高校は退学して高卒認定試験を受けるのも選択肢です。合格すれば、留年せずに高校を3年で卒業した場合と同じタイミングで進学できる可能性があります。
なお、高卒認定試験は高校在学中でも受験可能です。
また、高校ですでに取得した科目単位がある場合、該当科目の試験を免除できる点も特徴です。
高卒認定試験については、『通信制高校で取得できる高卒資格と高卒認定はどっちが良いの?メリット・デメリットも解説』も参考にしてください。
就職する
学費を払えないなど、経済的な理由で留年した場合は、高校を退学して就職するのも選択肢のひとつです。社会人として働くことで学ぶ意欲が高まり、再び高校卒業を目指したくなるかもしれません。
しかし、高校を退学すると最終学歴が「中卒」になってしまいます。そのため、就職先の選択肢が限定される可能性もあります。
働きながら通信制高校や定時制高校に通って高卒資格を得れば、次の就職先の選択肢が広がるでしょう。
よくある質問
最後に、高校の留年に関してよくある質問に回答します。
Q.留年は何回まで?
A.高校を留年できる回数に明確な基準はありません。各学校の規定によって定められているため、1回までとする学校もあれば、2回以上でも可とするケースもあります。
ただし、各学校で規定された留年の上限を超えると退学を言い渡されてしまうため、あらかじめ校則を確認しておきましょう。
Q.留年が決まるタイミングは?
A.留年が確定するタイミングに明確な定めはなく、各学校の基準によって異なります。例えば、出席日数を基準としている場合は、仮に成績が十分であっても、出席日数が下回った段階で通知されることがあります。
留年の可能性がある場合は、通常、先生から事前に通知されるため、突然、留年が通告されることは少ないです。赤点を取ったらすぐ留年が決定するわけではなく、補習授業や追加の課題提出など、留年を回避するための救済措置があることが一般的です。
Q.成績に1がついたら留年になる?
A.多くの高校では、成績に1がついたからといってすぐに留年になることはありません。
仮に成績で1を取ったとしても、先にあげたように、補習や追加課題提出などに取り組むことで留年を回避することも可能です。
しかし、課題や補習に取り組まなかったり、不真面目な態度を取ったりした場合は、留年の可能性が高まるため注意しましょう。
Q.留年する人の特徴は?
A.留年する人の特徴はそれぞれであり、出席日数や成績が原因である可能性が高いです。
例えば、学校の雰囲気や環境に合わず欠席が多くなる場合や、朝起きるのが苦手な人は、出席日数や成績不振が原因で留年につながりやすいです。
ただし、留年の可能性があっても、多くの学校では救済措置が設けられています。留年するかどうか不安になったら学校に相談しましょう。
まとめ
高校留年は、必要な単位を取得できるかどうかによって決まります。単位を得るために、定期テストで基準点を下回る成績を取らないようにし、出席日数を満たす必要があります。
留年が決定しても、在籍中の高校で同じ学年をやり直すだけでなく、定時制高校や通信制高校などの他の高校に転入する選択肢もあります。
通信制高校は、学校に毎日通う必要がないため、自分の生活スタイルに合った時間帯で学習を進めたい人におすすめです。
通信制高校について詳しく知りたい人は、『通信制高校とは?カリキュラムや全日制との違いをわかりやすく解説!』を参考にしてください。